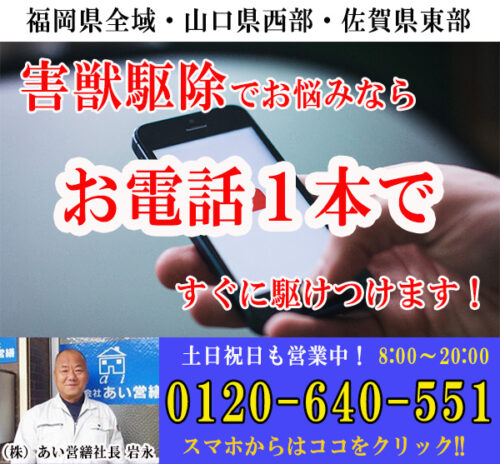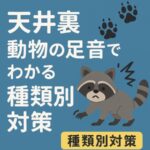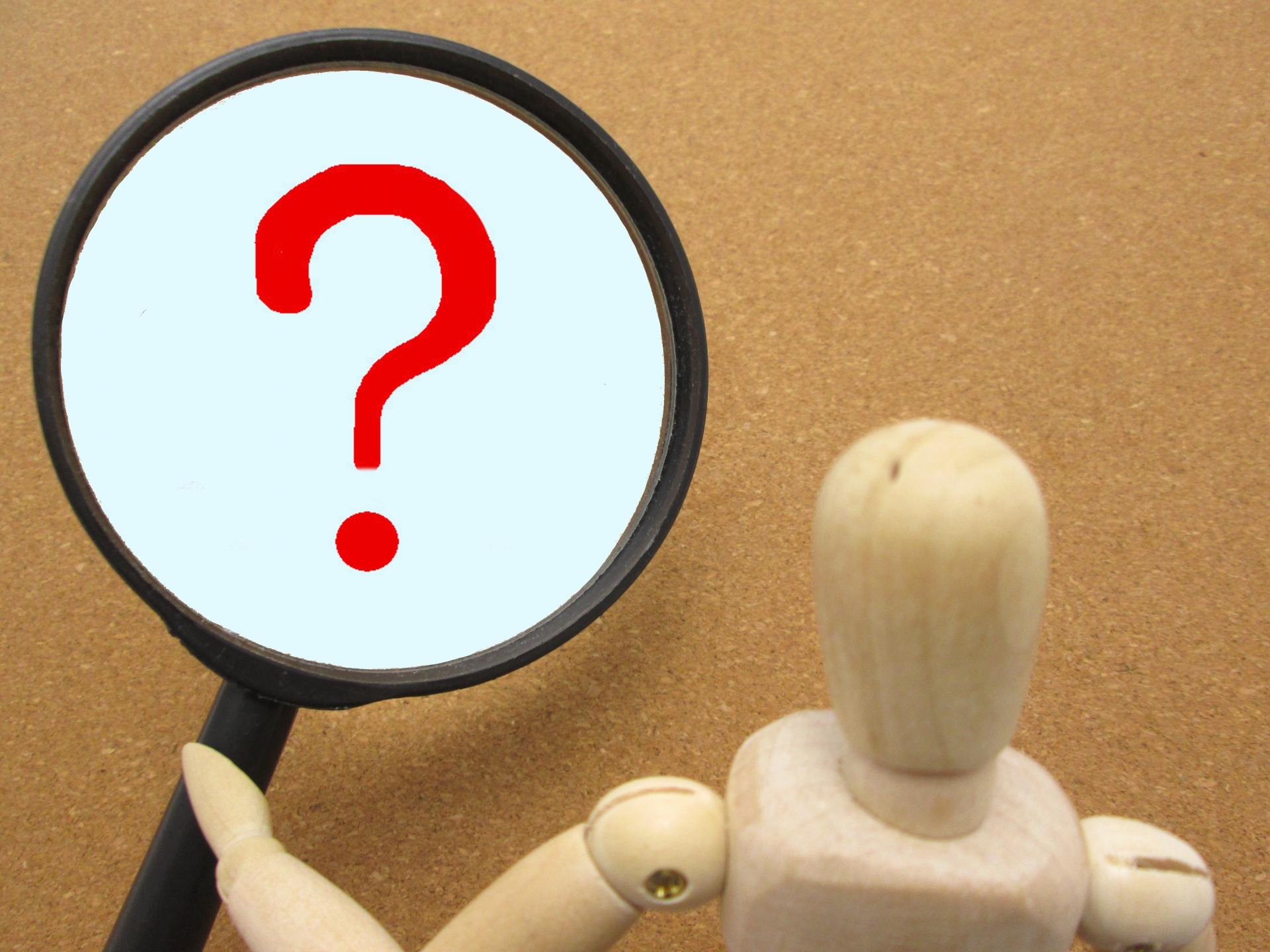北九州市小倉北区にお住まいの方で天井裏や床下に侵入した害獣でお困りの方は、地元の害獣駆除業者”あい営繕”にご相談ください。
当社はイタチやハクビシン、アライグマ、ネズミなどさまざまな害獣の駆除歴が20年以上の会社です。これまでの経験に基づいた駆除作業で害獣によるお悩みを解消いたします。
害獣は、民家において次のような被害を及ぼします。
- 夜行性なので夜中に屋根裏を走り回ることによる騒音問題
- 貯め糞の習性によるニオイ問題
- 糞尿による雑菌やカビの繁殖
- 害獣についたダニやノミが居住区に降りてくる
- 屋根裏で食べた小動物の死骸によるニオイや虫害
害獣の被害にあっていることに気づいても大きな問題ではないからと思い、駆除を考えない方もいらっしゃいます。
しかし問題を放置すると、屋根裏の木が腐ったりニオイやダニ・ノミの影響で住めなくなったりする恐れがあります。
そうなってからでは家の資産価値も落ちるうえに、日々の生活する場所に困ってしまうことになるケースもある為に早期の駆除が必要です。

北九州市小倉北区の皆さま、あい営繕代表の岩永と申します。害獣が屋根裏に棲みついていることに気づいた段階で、プロの業者にくじょを依頼することが大切です。
またご自身で駆除しようとする方もいらっしゃいますが、鳥獣保護法により駆除には許可が必要なため必ずプロの業者にご相談ください。
あい営繕の公式ホームページの屋根裏動物「イタチ・アライグマ」について
天井裏の幼獣に食べ物を運ぶ親害獣「テン」の動画・閲覧注意
突然ですが害獣と呼ばれる小動物はこのようにして餌を運びます。小倉北区でもイタチやテン、アライグマの生息が確認されていますので同じようなことが時期になると日夜行われています。
※害獣駆除業者の弊社調べ
獲物を持ち込む残酷なシーンもありますので苦手な方はスキップしてください。
北九州市小倉北区でも多い屋根裏への動物侵入被害

どの害獣も秋頃から外敵のいない戸建て住宅の屋根裏へとは入り込み、小倉北区でも1月頃になると頻繁に屋根裏に侵入してきて自分の巣にしようと虎視眈々と狙っています。
一旦棲みつかれてしまうとさまざまな被害を及ぼします。例えば夜間に屋根裏を害獣が走り回る音で眠れなくなったり、糞尿のニオイが居住区にまで降りてきて生活できなくなったりします。
害獣の被害はとても大きくなる可能性があるため、できるだけ早く駆除することが大切です。また糞尿に雑菌やカビが繁殖したり、ダニやノミが降りてきて人が咬まれる問題もあります。
何より4月頃になると天井裏では害獣の赤ちゃんが5匹前後生まれます。そうなると親イタチは餌を取りに外と天井裏を行ったり来たりで赤ちゃんが成獣になる8月頃迄、夜な夜な動物の運動会状態となってしまいます。

見えない天井裏で害獣などの生き物が棲みつくと様々なマイナスが生じてしまいますね。
北九州市小倉北区のホームページに屋根裏の害獣駆除のバナー広告を掲載しています。
※2023年3月現在
北九州市小倉北区で迷惑生物となる害獣はイタチやアライグマの他にも
侵入してくる動物は以下のような生き物が迷惑生物の害獣となっています。もちろん一つとして無駄な命はなく貴重な生き物ですが、「人」と同じ場所に住むには迷惑生物という意味合いです。
◉イタチ

◉ハクビシン

◉アライグマ

◉アナグマ

◉ハト(平和の象徴の鳩も糞害や鳴き声そして感染症の被害があります。)

◉ネズミ

◉コウモリ

北九州市の中でも新幹線の駅がある小倉駅周辺では北九州市の中でも一番の繁華街です。
会社のオフィスなど多く、動物侵入の例もいくつもあります。同様に住宅地への動物侵入のご相談も数多くあります。
あい営繕は上記の建物の屋根裏や床下に侵入してくる害獣に対応可能な専門の害獣駆除業者です。
【関連記事】市役所での害獣駆除対応と専門業者の活用法
害獣駆除の基礎知識
害獣駆除とは?基本的な考え方と法律
害獣駆除とは、人々の生活環境を脅かす野生動物を追い払ったり、侵入を防いだりするための取り組みを指します。
例えば、屋根裏に住みついたコウモリや、家庭菜園を荒らすイタチ、さらには家屋に侵入するネズミなど、さまざまな害獣が私たちの生活に影響を及ぼします。
これらの動物を放置すると、健康被害や住宅へのダメージが拡大する可能性があるため、早期の対応が重要です。
ただし、害獣駆除を行う際には、必ず法律に従って適切な方法を選ばなければなりません。日本では「鳥獣保護管理法」という法律があり、これにより多くの野生動物が保護されています。
この法律は、野生動物の乱獲を防ぎ、自然環境を守ることを目的としています。そのため、許可を得ずに動物を捕獲したり傷つけたりすることは禁じられています。
害獣駆除の基本的な考え方として、「動物を傷つけずに追い払うこと」が大切です。
たとえば、害獣が嫌がる匂いや音を利用して住みつきにくい環境を作ることや、侵入経路を塞ぐといった方法が推奨されます。
こうした取り組みを行うことで、法律を守りながら生活環境を改善することが可能です。
鳥獣保護法に基づく駆除の注意点
鳥獣保護法に基づいて害獣駆除を行う際には、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
まず、許可の必要性について知っておきましょう。
鳥獣保護法では、基本的に野生動物を捕獲するためには自治体からの許可が必要です。例えば、捕獲のために罠を設置する場合、事前に捕獲許可を申請する必要があります。
ただし、許可の手続きには時間がかかる場合もあるため、早めに申請することが重要です。
次に、駆除方法にも注意が必要です。許可を得ていない場合でも、追い払うこと自体は認められていますが、動物を傷つけない方法を選ばなければなりません。
たとえば、煙や強い香りで追い払う方法や、物理的な障壁を設けることで侵入を防ぐ方法が挙げられます。逆に、毒餌や殺傷を目的とした罠を使うと、法律違反となり罰則を受ける可能性があります。
さらに、駆除を行う際には地域のルールにも注意しましょう。
一部の自治体では、特定の動物に対する駆除活動を支援しており、捕獲器の貸し出しや専門業者の紹介などのサポートを提供している場合があります。これらの制度を活用することで、スムーズに害獣駆除を進めることができます。
最後に、動物たちも生態系の一部であることを忘れてはいけません。
駆除活動は必要最低限にとどめ、共存の道を模索することも重要です。環境全体を考えた対策を講じることで、自然を守りながら快適な生活を維持することができます。
害獣の種類と特性別対策
日本でよく発生する害獣の種類
害獣は、私たちの生活環境にさまざまな影響を与える動物たちのことです。特に日本では以下の害獣が問題となることが多いです。それぞれの特徴や被害、そして対策について解説します。
ネズミ
ネズミは通年発生する害獣で、特に住宅地や都市部で多く見られます。
狭い隙間から家屋に侵入し、食べ物を狙うだけでなく、配線をかじって火災の原因になることもあります。また、病原菌を媒介するため衛生面でも大きなリスクがあります。
対策としては、家の中に侵入させないことが最優先です。特に、2.5cmほどの隙間があれば通れるため、換気口や配管の隙間をしっかり塞ぎましょう。
また、食べ物を出しっぱなしにせず、ゴミ箱にはフタをするなどの衛生管理も大切です。
コウモリ
コウモリは主に5月から10月にかけて活動が活発になります。特に屋根裏や軒下などの狭い場所を好み、大量の糞尿を排出するため、臭いや衛生被害が深刻です。
糞には病原菌や寄生虫が含まれる可能性があり、健康被害のリスクもあります。
コウモリの対策としては、侵入経路の特定と遮断が重要です。1.5cm程度の小さな隙間でも侵入できるため、家の外周を細かくチェックし、パテや金網を使って隙間をふさぎましょう。
また、忌避剤やハッカ油を使用して、コウモリが嫌がる環境を作るのも効果的です。
ハクビシン
ハクビシンは、東日本を中心に見られる害獣で、果物や農作物を荒らすことで知られています。また、屋根裏や床下に住みつき、糞尿や鳴き声による被害をもたらします。
ハクビシン対策では、まず侵入経路を遮断することが大切です。特に屋根裏や換気口など、3cm以上の隙間を見逃さないようにしましょう。また、果物などの食べ物を屋外に放置しないことも重要です。
アライグマ
アライグマは全国で発生する害獣で、ゴミを荒らしたり農作物に被害を与えたりします。木登りが得意で、10cm以上の隙間があれば侵入できるため、注意が必要です。
対策としては、家の周りのゴミ管理を徹底することが重要です。蓋つきのゴミ箱を使用し、ゴミの日以外は屋外に出さないようにしましょう。また、侵入防止用の金網やフェンスを設置するのも効果的です。
イタチ
イタチは西日本でよく見られ、屋根裏や床下に侵入して巣を作ります。糞尿の被害や悪臭、さらにはペットや家畜を襲うこともあります。
対策として、侵入経路を徹底的に塞ぐことが基本です。3cm以上の隙間を塞ぎ、忌避剤を活用して住み着きにくい環境を作りましょう。
害獣の特徴と侵入経路を知る重要性
害獣対策を成功させるには、それぞれの動物の特徴を知り、侵入経路を把握することが非常に重要です。
例えば、ネズミは小さな隙間を見つけて家の中に入り込み、コウモリは屋根裏や通気口を好みます。これらの知識があれば、被害を未然に防ぐための適切な対策が取れます。
侵入経路を特定する際には、家の外周や屋内をじっくりと観察し、小さな隙間や破損箇所を見逃さないようにしましょう。
また、侵入経路を塞ぐだけでなく、害獣が嫌がる環境を整えることも大切です。これにより、害獣が家に近寄りにくくなり、長期的な被害の予防につながります。
害獣対策は一度だけで終わらせず、定期的に点検しながら継続して取り組むことが重要です。家族や住環境を守るために、適切な知識と対策を持って害獣に対応しましょう。
害獣駆除の方法とステップ解説
自分でできる害獣駆除の具体的な手順
害獣駆除を自分で行う際には、適切な手順を踏むことが大切です。
ただ闇雲に駆除を試みるのではなく、計画的に対策を進めることで、より効果的に害獣を追い出すことができます。ここでは、特に初心者にも分かりやすい方法を解説します。
煙や刺激臭を利用した追い出し
まず、害獣が住みついている可能性がある場所を特定しましょう。
害獣が好む場所は、屋根裏、床下、換気扇の奥などの暗くて静かな場所です。物音や臭いがする場所があれば、その近辺をチェックしてください。
次に、煙や刺激臭を使って害獣を追い出します。燻煙剤(市販の「バルサン」など)や忌避剤を使うのがおすすめです。
煙は害獣が嫌がるため、巣から出て行くきっかけを作ります。使用する際には、必ず換気扇を止め、密閉状態を保ちながら煙を充満させましょう。
一方、忌避剤はハッカやナフタリンなどの成分を利用して、害獣にとって居心地の悪い環境を作ります。これらを害獣が通りそうな場所や巣の近くに設置することで、追い出し効果が期待できます。
侵入防止のための隙間対策
害獣を追い出した後に最も重要なのが、侵入経路を完全に塞ぐことです。多くの害獣は1〜3cmの隙間があれば侵入できます。
特に窓のサッシ部分、換気扇の隙間、屋根と壁の間など、気付きにくい場所を重点的にチェックしてください。
隙間を塞ぐためには、シーリング材や金網が便利です。細かい隙間にはシーリング材を注入し、換気扇や通気口には目の細かい金網を設置しましょう。
また、エアコン配管の通り道にはパテを使って密閉するのが効果的です。
これらの対策を取ることで、新たな害獣の侵入を防ぎ、問題を根本から解決することができます。侵入経路を見逃さず、家全体を守る意識を持つことが大切です。
害獣駆除は、一度追い出して終わりではなく、その後の再発防止が鍵となります。
自分でできる方法を計画的に実践しながら、状況に応じて専門業者のサポートを活用するのも一つの手段です。害獣被害を未然に防ぎ、快適な生活環境を維持しましょう。
害獣駆除の費用と相場
軽度から重度の被害別の費用例
害獣駆除の費用は、被害の程度や駆除方法によって大きく変わります。軽度な被害の場合は比較的安く済むこともありますが、重度の被害では費用がかさむことが多いです。
以下は被害の程度に応じた費用の例です。
軽度の被害(~8万円程度)
軽度の被害とは、害獣が建物内に短期間侵入しただけの場合や、糞尿の掃除が少量で済むケースです。
この程度の被害では、隙間を塞ぐ簡単な修繕や、少量の糞尿の清掃・消毒が主な作業内容となります。例えば、屋根裏にコウモリが少数侵入している場合や、ネズミの足跡が見られる程度のケースです。
この場合、自力駆除が可能であれば、材料費(忌避剤やシーリング材)を含めて数千円から1万円程度で対応可能です。
ただし、専門業者に依頼すると、調査費用や基本料金を含めて3万〜8万円程度になることがあります。
中程度の被害(8万〜15万円程度)
中程度の被害とは、害獣が建物内に住み着いており、糞尿の量が増えているケースです。
例えば、屋根裏全体にネズミが巣を作ったり、コウモリが集団で棲みついていたりする場合が該当します。このような場合、駆除だけでなく、糞尿の清掃と消毒、侵入経路の修繕が必要になります。
専門業者に依頼すると、こうした作業をすべて含めて8万〜15万円程度が相場です。被害が広範囲に及んでいる場合や、作業が複雑な場合はさらに費用がかかる可能性があります。
重度の被害(15万〜40万円以上)
重度の被害では、害獣の侵入によって天井が抜け落ちるなど建物の構造に深刻なダメージを受けることがあります。
この場合、駆除費用に加え、修繕費用や再発防止対策の費用が発生します。
たとえば、アライグマが床下や屋根裏で長期間過ごしていた場合、糞尿の臭いが建物全体に広がり、消毒や清掃だけでは不十分なことがあります。
このようなケースでは、費用は20万円を超えることが一般的です。
自力駆除と業者依頼のコスト比較
害獣駆除は、自力で行うか専門業者に依頼するかで費用が大きく変わります。それぞれのコストの違いを見てみましょう。
自力駆除のコスト
自力駆除の場合、必要な費用は主にグッズや材料費です。燻煙剤、忌避剤、シーリング材、金網などを購入すると、合計で1万円程度が目安です。
これらを使用して、自分で駆除や隙間の修繕を行うことができます。ただし、作業に手間がかかるうえ、不十分な対応では再発する可能性が高いです。
また、害獣に直接触れるリスクがあるため、感染症などにも注意が必要です。
業者依頼のコスト
専門業者に依頼すると、初期費用として調査や駆除にかかる基本料金が3万〜8万円程度かかることが一般的です。
被害の程度によって費用は変動しますが、糞尿の清掃や侵入防止策を含めた総合的な対応が期待できます。また、業者によっては再発防止の保証をつけてくれる場合もあり、長期的な安心感があります。
考察
自力駆除は初期費用を抑えられるメリットがありますが、手間やリスクを伴います。
一方で、専門業者に依頼すれば、費用は高くなるものの、再発防止や徹底的な対応が可能です。害獣の種類や被害の程度によって最適な選択肢を検討しましょう。
また、早めに対策を講じることで、被害を最小限に抑えることができます。
専門業者に依頼する際のポイント
害獣駆除業者を選ぶ際の注意点
害獣駆除を専門業者に依頼する場合、適切な業者を選ぶことがとても大切です。
信頼できない業者に依頼すると、思わぬトラブルや高額な料金請求を受ける可能性があります。以下の点に注意して選びましょう。
-
見積もりの透明性を確認する
まず、業者に見積もりを依頼した際、作業内容や費用の内訳が明確に記載されているかを確認してください。例えば、「駆除費用」だけでなく、「清掃費用」や「再発防止策の費用」など、項目ごとに分かれていることが重要です。不明確な料金設定がある場合は、別の業者に見積もりを依頼するのが良いでしょう。
-
保証内容をチェックする
害獣駆除後の再発保証を提供している業者も多くあります。保証期間や内容を事前に確認し、再発時に追加料金がかかるかどうかを確認することが大切です。 -
口コミや評判を調べる
インターネット上の口コミや評判も参考にしましょう。実際に利用した人の感想から、業者の信頼性や対応力を判断できます。ただし、極端に良い評価や悪い評価は慎重に判断し、複数の意見を比較することをおすすめします。
自治体が提供する害獣駆除サポートとは?
市役所や保健所でできること
害獣駆除において、自治体(市役所や保健所)が提供するサポートは、個人での対応が難しい場合に非常に役立ちます。
ただし、自治体によって内容が異なるため、事前に確認することが大切です。一般的には以下のようなサービスを提供しています。
-
害獣駆除のアドバイス
市役所や保健所では、害獣駆除に関する相談窓口を設けていることがあります。ここでは、自宅でできる駆除方法や予防策についてアドバイスを受けることができます。また、害獣の種類に応じた具体的な対策(例えばネズミやコウモリの侵入を防ぐ方法)を教えてもらえることもあります。
-
駆除業者の紹介
自力で対応が難しい場合、自治体は信頼できる駆除業者を紹介してくれることがあります。これは、初めて駆除業者を探す人にとって特に役立ちます。ただし、自治体が紹介する業者を利用する際も、費用や対応内容をしっかり確認しましょう。
-
捕獲許可の申請窓口
鳥獣保護法の規定により、許可なしで害獣を捕獲することはできません。市役所では、捕獲許可の申請を受け付けており、手続きの方法を案内してくれます。これにより、法令を守りながら安全に駆除活動を進めることが可能です。
補助金や捕獲器貸し出し制度の活用方法
自治体によっては、害獣駆除に関連する補助金や捕獲器の貸し出しを行っている場合があります。これらの制度を利用すれば、費用を抑えながら効率的に対策を進めることができます。
-
補助金制度の利用
一部の自治体では、害獣駆除にかかった費用を一部負担してくれる補助金制度を設けています。たとえば、捕獲器の購入費や業者への駆除依頼費の一部を補助してもらえる場合があります。ただし、この制度は地域や対象害獣によって適用条件が異なるため、詳細を確認する必要があります。
-
捕獲器の貸し出し
自治体が無料または低料金で捕獲器を貸し出してくれる場合があります。特に、ネズミやアライグマなどの捕獲が必要な場合、このサービスは非常に有効です。ただし、捕獲器を使うには自治体への申請が必要な場合が多いので、事前の手続きを忘れないようにしましょう。
-
注意点
捕獲後の処理については、自治体では対応してくれない場合があります。害獣の処分には専門的な知識が必要なため、捕獲後の対応についてもあらかじめ計画しておくことが重要です。
考察
自治体のサポートは、害獣駆除の初期段階で大いに役立ちます。
ただし、全ての地域で同じ内容のサービスが受けられるわけではないため、自分の住んでいる自治体の制度を事前に確認することが大切です。
また、補助金や捕獲器の貸し出しを上手に活用することで、費用を抑えつつ効率的な駆除を実現することができます。
自治体のサポートを最大限に活用しながら、必要に応じて専門業者の力も借りることで、安全で確実な害獣駆除を行いましょう。
害獣被害を防ぐ予防策
害獣を寄せ付けない家づくり
害獣の被害を防ぐためには、そもそも家に近寄らせない工夫が重要です。
これには隙間を塞ぐことや、ゴミの管理を徹底することが含まれます。また、害獣が嫌がる環境を作るためのアイデアを取り入れることも効果的です。以下に具体的な方法を説明します。
隙間対策
害獣が侵入する主な原因は、家の構造にできた小さな隙間です。
例えば、ネズミやコウモリは1〜2cm程度の隙間でも入り込むことができます。屋根や外壁、配管の周りなど、見落としがちな箇所を定期的にチェックすることが大切です。
隙間を塞ぐためには、以下のような材料を活用すると良いでしょう。
- シーリング材: 窓枠や配管周りなどの細い隙間に適しています。
- 金網: 換気口や排水口など、空気の流れが必要な場所に使用すると便利です。
- パテ: エアコンの配管スペースなど、形が不規則な隙間に有効です。
また、隙間を塞ぐ際には、害獣が既に住みついていないか確認してから行うことを忘れないようにしましょう。
ゴミ管理のポイント
ゴミは害獣にとって格好の餌場になります。特にアライグマやネズミは、家庭ゴミから食べ物を探し出すのが得意です。
ゴミを適切に管理することは、害獣を家に寄せ付けないための基本的な対策です。
具体的には、以下のポイントに注意してください。
- ゴミ箱にしっかり蓋をする: 害獣が簡単に開けられない頑丈な蓋付きのゴミ箱を使いましょう。
- 生ゴミは密閉して捨てる: 臭いが外に漏れないよう、生ゴミはビニール袋に入れてからゴミ箱に捨てると効果的です。
- ゴミの日以外は外に出さない: ゴミを外に放置すると、害獣が餌場と認識してしまう可能性があります。
動物が嫌がる環境を作るアイデア
害獣を寄せ付けないためには、動物が嫌がる環境を意識的に作ることが効果的です。以下のアイデアを参考にしてみてください。
刺激臭や動体センサーライトの活用
害獣は嗅覚が敏感であるため、特定の匂いを嫌がることが知られています。
ハッカ油やナフタリンを使った忌避剤は、害獣が侵入する場所に置くだけで効果を発揮します。これらを換気口や庭の周囲に配置すると良いでしょう。
また、動体センサーライトも有効です。多くの害獣は暗い場所を好むため、急にライトが点灯することで驚いて逃げることがあります。
庭や家の周囲に動体センサーライトを設置して、夜間の害獣侵入を防ぎましょう。
草木の手入れを行う
庭の草木が生い茂っていると、害獣が隠れる場所を作ってしまうことになります。家の周囲は定期的に剪定を行い、見通しを良くしておきましょう。特に家に近い低木は要注意です。
考察
害獣被害を防ぐには、侵入を許さない物理的な対策と、害獣が寄りつきにくい環境を作る工夫が欠かせません。
隙間を塞いだりゴミを適切に管理したりする基本的な対策を徹底しながら、忌避剤や動体センサーライトといった手軽なグッズを活用するのもおすすめです。
また、定期的なチェックとメンテナンスを行うことで、長期的な被害防止につながります。家族の安全を守るためにも、これらの予防策をぜひ実践してみてください。
害獣駆除でよくある質問(FAQ)
Q1.害獣駆除はどれくらいの時間がかかる?
A1.害獣駆除にかかる時間は、被害の状況や駆除する害獣の種類によって異なります。
例えば、屋根裏に数匹のネズミがいる場合は、数時間で駆除が終わることもありますが、大量のコウモリが住みついている場合や糞尿の清掃が必要な場合は、1日以上かかることもあります。
業者に依頼する場合は、まず現地調査を行い、その後、駆除作業や清掃を進めるのが一般的です。これにより、駆除全体で数日から1週間程度かかることがあります。
一方で、自力で駆除する場合は、準備や作業に時間がかかり、さらに効果を実感するまで数日以上かかることが多いです。
考察
駆除にかかる時間を短縮するには、早めに対応することがポイントです。害獣の発見が遅れると被害が拡大し、駆除にも時間がかかります。
定期的な点検と迅速な対応が、時間と労力を節約する鍵です。
Q2.自力で駆除するのと業者に依頼するの、どちらがおすすめ?
A2.どちらが適しているかは、被害の程度や状況によります。自力駆除と業者依頼のメリット・デメリットを比較してみましょう。
自力駆除のメリットとデメリット
メリット
- 費用を抑えられる。
- 自分のペースで対応できる。
- 市販の駆除グッズが手軽に手に入る。
デメリット
- 知識や経験がないと効果が不十分な場合がある。
- 害獣や糞尿に直接触れるリスクがある。
- 時間と労力がかかる。
業者依頼のメリットとデメリット
メリット
- プロの知識と技術で確実に駆除できる。
- 再発防止の対策も含めて対応してもらえる。
- 安全かつ効率的に作業が進む。
デメリット
- 費用がかかる。
- 業者選びに手間がかかる場合がある。
考察
軽度の被害や駆除が簡単な場合は自力でも十分対応可能です。しかし、被害が広範囲に及んでいる場合や、害獣が多い場合は業者に依頼する方が確実です。
自分の状況に合わせて選択すると良いでしょう。
Q3.害獣の糞尿被害の対処法とは?
A3.害獣の糞尿被害は、放置すると悪臭や衛生面の問題を引き起こします。適切に処理するためには、以下の手順を守ることが大切です。
糞尿被害の対処手順
-
保護具を着用する マスクやゴム手袋、保護メガネを装着し、直接触れないようにします。
-
糞尿を収集する ほうきとちりとりを使い、糞尿を集めてビニール袋に入れ、しっかり口を閉じます。
-
消毒を行う 糞尿があった場所を漂白剤やアルコールでしっかり拭き取り、病原菌や寄生虫を除去します。
-
再発防止対策を講じる 害獣の侵入経路を塞ぎ、同じ場所で被害が起きないようにします。
考察
糞尿被害の処理は、健康リスクを伴うため慎重に行う必要があります。大規模な被害の場合は、清掃や消毒を業者に依頼するのも一つの方法です。
また、被害が広がる前に早めの対応を心がけることが重要です。
害獣駆除を成功させるためのまとめ
効果的な害獣駆除のポイント
害獣駆除を成功させるためには、適切な計画と実行が必要です。効果的な駆除には、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
-
害獣の種類と侵入経路を特定する
まず、どの害獣が被害を与えているのかを特定することが重要です。ネズミ、コウモリ、アライグマなど、それぞれの害獣に適した対策が必要です。また、侵入経路を突き止めることで、根本的な再発防止策を講じることができます。
-
適切な道具や方法を選ぶ
市販の忌避剤や燻煙剤を使用する場合は、害獣が嫌がる匂いや煙を効果的に使うことがポイントです。例えば、コウモリにはハッカ油や燻煙剤が有効で、ネズミには捕獲器や毒餌が適しています。害獣の特性に合った道具を選びましょう。
-
安全を最優先に考える
害獣の糞尿には病原菌が含まれている可能性があるため、駆除や清掃作業を行う際にはマスクや手袋を着用し、直接触れるのを避けることが大切です。危険を感じる場合は無理せず、専門業者に依頼するのも一つの選択肢です。
早期発見と適切な対処の重要性
害獣駆除を成功させるには、早期発見と迅速な対応が何よりも大切です。被害が進行してしまうと、駆除だけでなく修繕や清掃の手間と費用も増えるため、初期段階での対応が理想的です。
なぜ早期発見が重要なのか?
害獣は、気付かないうちに家の中で活動し、被害を広げることがあります。例えば、ネズミはわずかな隙間から侵入し、電気配線をかじることで火災リスクを高めます。
また、コウモリの糞尿が天井裏に蓄積されると、建物の腐食や悪臭の原因にもなります。早期に発見して対応することで、これらのリスクを未然に防ぐことができます。
適切な対処法とは?
発見した時点で、以下のような対処法を検討しましょう。
- 軽度の被害: 自力で忌避剤や捕獲器を使って対応する。
- 中度以上の被害: 業者に相談して、駆除や清掃、再発防止の対策を依頼する。
特に、侵入経路の遮断や害獣が嫌がる環境作りを徹底することが、再発を防ぐうえで効果的です。
考察
害獣駆除は、ただ追い払うだけでは不十分です。被害を防ぐためには、早期発見と的確な対応が不可欠です。また、駆除後の再発防止策にも注意を払いましょう。
これにより、家を害獣から守り、安心して暮らせる環境を維持できます。定期的な点検や予防策を習慣化することで、長期的な効果が期待できます。
自分でできる対策を試しつつ、必要に応じて専門業者の力を借りることも検討してください。
小倉北区が地元の害獣駆除専門業者”あい営繕”の特徴
保証期間があるため安心
あい営繕の大きな特徴は、害獣駆除後に3年の長期保証期間があることです。
害獣駆除の作業後、3年以内に再び害獣被害にあわれた場合無料で作業をやり直しいたします。
一般的に作業後3年以内に再び害獣被害にあわなかった場合、それ以降直接の外的要因が無い限り10年程度は被害にあわないとされています。
つまり作業から3年間は作業の効果を検証する期間と言えるため、あい営繕では保証期間を3年としています。
あい営繕は的確な駆除作業に自信を持っておりますが、初めてご依頼される場合は少なからず不安を覚えるものではないでしょうか。
保証期間があることで、お客様としても安心してご依頼いただけるかと思います。
害獣駆除のノウハウ以外にも質の高い接客対応とサービス
あい営繕は、お客様のご希望を察知して気持ちのいい対応をすることを心がけております。
また害獣の被害にあわないために必要なものをご提案することがございますが、不要なものを押し売りするようなことは一切ございません。
1人のプロとして、誇りと責任をもって対応させていただきます。
調査見積もりは無料
害獣駆除の料金を確定するには、小倉北区内のどちらでもお伺いできます。お伺いしての現地調査が必要です。
あい営繕では、現地調査の見積もりには料金をいただいておりません。
見積もりが有料だと、あい営繕の質の高い接客対応を知っていただく機会の損失に繋がると考えております。
ご依頼の際には少なからず不安を感じるものですので、まずは無料見積もりをいただいてその際にスタッフの対応をチェックいただければと思います。
もちろん、同業の害獣駆除業者への相見積もりをしていただいても問題ございません。それでもあい営繕を選んでいただける自信がございます。

害獣駆除業者”あい営繕”の所有資格
・建築物ねずみ昆虫等防除業(福岡県知事登録 福岡県 28 ね 第352号)
・しろあり防除施工士(第12815号)
・蟻害・腐朽検査員(九州-福岡県-15-0083)
・防除作業監督者(防第14418号)
・ペストコントロール技能師
・特定科学物質・四アルキル鉛等作業主任者
・増改築相談員(登録番号:101512)
・わな猟 狩猟免状 八農わな猟17第0033号
北九州市小倉北区について
北九州市小倉北区はショッピングモールや飲食店、居酒屋、農産物直売所などで活気にあふれた繁華街です。
また小倉城がある勝山公園や閑静な住宅街など、さまざまな街並みを楽しめるのが魅力的です。
外せないスポットと言えば旦過市場でしょう。アンコウやフグといった高級魚からアジやイワシまで販売されています。
※2022年に2度の火災に見舞われたこと地元民としても心を痛めました。旦過市場のお店で営業が再開されてからは以前より行く回数が増えました。
食べ歩きもできるので、地元民から観光客でいつもにぎわっています。

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
以下に小倉北区の対応エリアを記載しておきます。
北九州市小倉北区で害獣駆除のご相談がありましたらお気軽にあい営繕にご相談下さいませ。
北九州市小倉北区の対応エリア
藍島・青葉・赤坂海岸・赤坂・浅野・朝日ケ丘・足原・愛宕・足立・泉台・板櫃・板櫃町・井堀・今町・鋳物師町・魚町・宇佐町・馬島・江南町・大田町・大手町・大畠・鍛冶町・片野新町・片野・金田・上到津・上富野・香春口・神岳・貴船町・木町・京町・清水・霧ケ丘・金鶏町・熊谷・熊本・黒住町・黒原・黄金・許斐町・米町・小文字・紺屋町・菜園場・堺町・三郎丸・皿山・町・山門町・重住・篠崎・下到津・下富野・昭和町・白銀・白萩町・神幸町・新高田・親和町・寿山町・城内・城野団地・末広・須賀町・砂津・船頭町・船場町・高尾・高浜・高坊・高見台・高峰町・竪林町・竪町・田町・大門・常盤町・富野・富野台・中井口・中井浜・中井・中島・中津口・長浜町・西港町・萩崎町・原町・馬借・日明・東篠崎・東城野町・東港・平松町・古船場町・弁天町・真鶴・緑ケ丘・南丘・三萩野・都・妙見町・室町・明和町・山田町・吉野町・若富士町