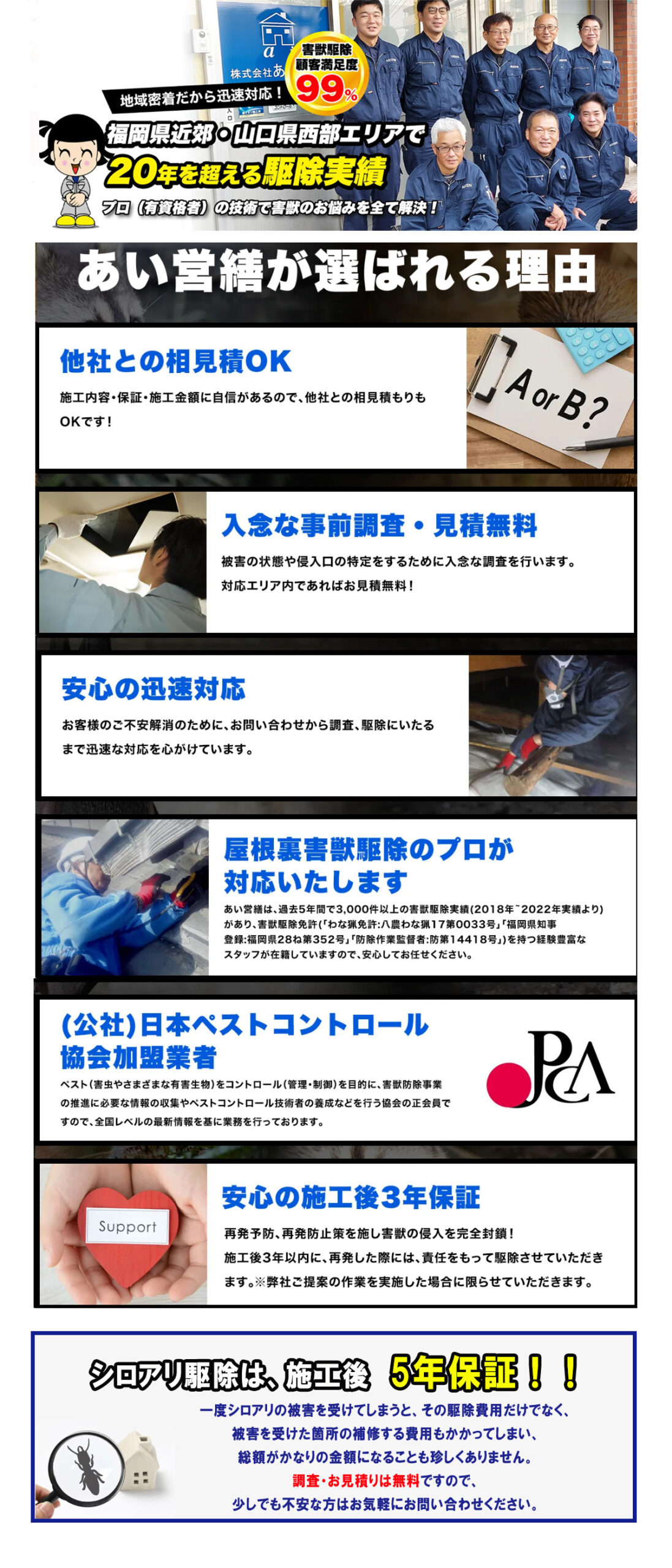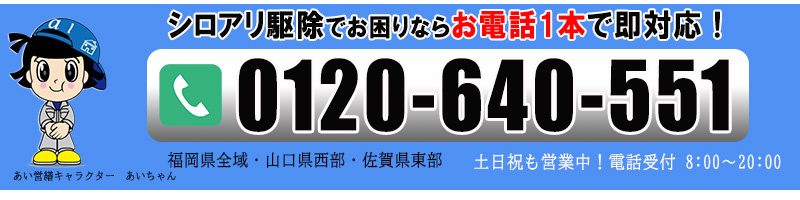特徴② 高さのある基礎で木部を守る

家の土台となる基礎の高さは、シロアリ対策においても重要なポイントです。
実は、地面から木の部分までの距離が短いと、湿気や雨の影響を受けやすくなり、シロアリにとって居心地の良い環境になってしまいます。
基準は30cm以上、理想は40cm
建築基準法では、基礎の高さを30cm以上にするよう定められています。
さらに、住宅ローンの技術基準として知られる「フラット35」では、地面から木材までの高さを40cm以上確保することが推奨されています。
この高さがあることで、地面からの湿気や雨の跳ね返りが直接木材に届きにくくなります。
木材が湿ると、シロアリが集まりやすくなるだけでなく、腐れやカビの原因にもなります。そのため、基礎の高さは見た目以上に大切な設計ポイントです。
見えない部分こそ丁寧に考える
基礎の高さが十分にあると、床下の通気性も良くなり、湿気がこもりにくくなります。
これがシロアリ対策につながるだけでなく、家全体の耐久性にもプラスに働きます。見た目では気づきにくい部分ですが、だからこそ、家を建てる前にしっかり考えておきたいポイントです。
高さのある基礎は、シロアリを遠ざけるための「物理的なバリア」とも言えます。建築時に少し気を配るだけで、将来の大きな安心につながるので、ぜひ取り入れておきたい工夫です。
特徴③ 風通しと乾燥が確保されている

シロアリは湿気を好む生き物です。じめじめとした環境はシロアリにとって快適で、木材の中にもぐり込んで被害を広げる原因になります。
だからこそ、家の中や床下をできるだけ乾燥した状態に保つことが、シロアリ対策としてとても効果的です。
風通しのよい設計で湿気を逃がす
家を建てるときには、風の流れを意識した設計が大切です。
窓の配置を工夫したり、通気性のある間取りにすることで、室内の空気がよく循環するようになります。
特に、北側や湿気がたまりやすい場所に換気の工夫をするだけでも、湿度のコントロールに大きな差が出ます。
また、床下や押し入れ、クローゼットといった閉ざされた空間は、風が通りにくく湿気がこもりがちです。
こうした場所に通気口や換気装置を設けることで、湿度が高まりすぎないようにすることができます。
外壁や床下にも通気の工夫を
さらに、家の外側の構造でも通気性を意識した工法があります。
たとえば、外壁と断熱材の間に空間を設けて空気を通す「外壁通気工法」は、壁の内部に湿気がこもらないようにするための工夫です。
この仕組みにより、壁の中まで乾燥した状態を保ちやすくなり、シロアリが寄りつきにくくなります。
床下も同じように、風の通り道をつくることが大切です。床下換気口や換気ファンを設置することで、空気がよどまない環境を保てます。
風通しと乾燥を意識した設計は、快適な住まいづくりにもつながるため、シロアリ対策だけでなく暮らしやすさにも貢献します。
乾燥した空間をつくることは、シロアリ対策の基本です。湿気をためない工夫を家のあちこちに取り入れて、安心して暮らせる住まいを目指しましょう。
特徴④ 雨漏りしにくい外壁・屋根

シロアリが寄ってくる原因のひとつに、「湿気」があります。
その中でも、見落とされがちなのが雨漏りです。家の中に水分が入り込むことで、湿気がたまりやすくなり、シロアリにとって住み心地の良い環境ができあがってしまいます。
雨漏りはシロアリを呼び寄せるサインに
たとえ小さな雨染みでも、長い間放置されれば木材が湿り、シロアリにとって格好の餌場になります。特に柱や梁などの構造部分が湿ってしまうと、家の強度にも影響を与えるため注意が必要です。
さらに、湿気がたまることでカビや腐れの原因にもなり、家全体の劣化スピードが早まってしまう恐れもあります。
だからこそ、雨漏りのリスクを減らすことは、シロアリ対策としても非常に重要です。
耐久性のある外壁・屋根材を選ぶ
家を建てる際には、雨に強い素材を選ぶことがポイントになります。
たとえば、タイル外壁は防水性が高く、長持ちしやすいため雨漏りを防ぎやすいとされています。また、瓦屋根も水をはじく力が強く、しっかりと施工されていれば雨水の侵入を防いでくれます。
最近では、メンテナンスの手間が少ない高耐久素材も増えてきています。初期費用は少しかかるかもしれませんが、長く安心して暮らすためには費用対効果の高い選択といえるでしょう。
シロアリから家を守るには、湿気の入り口をつくらないことが基本です。外壁や屋根選びの段階から、防水性のある素材を意識することが、トラブルを未然に防ぐ大切な一歩になります。
特徴⑤ 点検しやすい床下構造

シロアリの被害は、床下などの目に見えない場所から進行することが多いため、早期発見がとても大切です。そのためにも、床下を点検しやすい家にしておくことが、シロアリ対策の基本となります。
点検口があると見えない場所にも目が届く
家の床下に「点検口」が設けられていると、専門業者が床下の状況をすぐに確認できるようになります。
点検口がない家では、点検のたびに大がかりな作業が必要になってしまうため、手間も費用もかかります。
点検口があれば、基礎部分や木材の状態を定期的に確認できるだけでなく、水道や排水管の異常にも気づきやすくなります。
湿気の原因となる水漏れなども早めに発見できるため、シロアリの住みにくい環境を維持しやすくなります。
住宅基準でも推奨されている設計
国が定めた住宅ローンの技術基準「フラット35」でも、床下点検口の設置が推奨されています。
これは、家の健康を長く保つうえで、点検のしやすさが非常に重要だとされているからです。
点検しやすい構造にしておくことは、シロアリに限らず、家全体のトラブルを早く見つけることにもつながります。
将来のメンテナンス費用を抑えるためにも、見えない場所への配慮を忘れずに計画しておくことが大切です。
特徴⑥ 定期点検・駆除で早期発見

シロアリから家を守るためには、予防だけでなく「見つけること」もとても重要です。
いくら事前に対策をしていても、完璧に防げるとは限りません。だからこそ、定期的な点検と必要に応じた駆除処理が欠かせません。
駆除剤の効果は永遠ではない
一般的なシロアリ駆除剤は、一度使えば一生効果が続くわけではありません。
多くの場合、効果の持続期間は3〜5年程度です。時間が経つと薬剤の効力が弱まり、再びシロアリが侵入してくる可能性があります。
そのため、家を建ててからも定期的に駆除剤を再散布する必要があります。特に床下などの湿気がたまりやすい場所は、こまめな点検と処置が安心につながります。
プロによる点検と、住宅会社選びもカギ
自分で点検するのは難しい場所も多いため、専門業者によるチェックがおすすめです。
シロアリの専門家は、被害の兆候を見逃さずに確認してくれますし、必要な処置もスムーズに行ってくれます。
また、家を建てるときには、アフターメンテナンスに力を入れている住宅会社を選ぶことも大切です。
点検や防除を定期的に行ってくれる会社であれば、入居後の不安も減ります。半年や1年ごとに点検の案内がある会社なら、特に安心です。
家を建てるときには、完成後の「管理」まで考えておくことがポイントです。定期点検と再処理をしっかり行うことで、長く安心して暮らせる住まいを実現できます。
特徴⑦ 予防スプレーなど市販薬剤の活用

シロアリ対策というと大がかりな工事を思い浮かべるかもしれませんが、実は市販の薬剤でも手軽にできる予防方法があります。
とくに新築時やリフォームのタイミングに加えて、住んでからのケアとしても取り入れやすいのが「シロアリ予防スプレー」です。
スプレータイプなら気軽に使えて便利
市販されているスプレーは、シロアリが好む木材や紙類に直接吹きかけて使えるようになっています。
ホームセンターやネットでも手に入るので、初めての方でも試しやすいアイテムです。室内の木製部分や、床下の木材に使うと効果的です。
ただし、スプレーの多くは屋外で使用する場合、雨などで薬剤が流れてしまうことがあります。そのため、数か月ごとに定期的な再散布が必要になります。
補助的な手段として取り入れる
予防スプレーは、あくまで「補助的な対策」です。
シロアリが完全に侵入できないわけではありませんが、ちょっとした手間でリスクを減らすことができます。とくに、庭まわりに木製のプランターや倉庫がある家庭にはおすすめです。
普段からこまめに散布する習慣をつけておけば、シロアリの早期発見にもつながります。大切な家を守るために、自分でできる範囲の予防策として活用してみてはいかがでしょうか。
特徴⑧ 敷地内に木材・ダンボールがない

意外と見落とされがちですが、敷地内に置かれているものがシロアリを引き寄せてしまうことがあります。特に木材やダンボールなどは、シロアリにとって格好のエサになるため注意が必要です。
木や紙はシロアリの大好物
シロアリは、木材だけでなく紙類も好んで食べます。
庭に古い木材や使わなくなったダンボールを置きっぱなしにしていると、それだけでシロアリの活動エリアを広げてしまうことになりかねません。
さらに、雨に濡れて湿った状態になると、シロアリにとってはより快適な環境になります。
たとえば、工事のあとに残った廃材や、ガーデニング用に使った枕木なども油断できません。どれも一度シロアリが住みつくと、そこから家の中に侵入してくる可能性があります。
保管時のひと工夫が大切
どうしても一時的に木材やダンボールを置いておく場合は、いくつか気をつけたいポイントがあります。
まず、地面に直接置かないこと。レンガや棚などを使って地面から少し浮かせて保管すれば、シロアリが近づきにくくなります。
また、風通しの良い場所を選ぶことも大切です。湿気がこもる場所に置くと、たとえ短期間でもシロアリの温床になることがあります。
家を建てたあとも、周囲の環境を清潔に保つことがシロアリ対策になります。不要なものは早めに片づけ、置く必要があるときは工夫をする。それだけでも、シロアリのリスクを減らすことができます。
特徴⑨ 湿気の少ない土地選び

家づくりを考えるとき、多くの人は立地や交通の便を重視しますが、実は「湿気の少ない土地かどうか」も大切なチェックポイントです。
シロアリは湿った環境を好むため、土地の選び方次第でリスクが大きく変わってきます。
湿気がたまりやすい場所は要注意
シロアリが住みつきやすいのは、川沿い・低地・山間部など湿気がこもりやすい場所です。
これらのエリアでは、地盤が緩かったり、雨水がたまりやすかったりするため、建てた家の床下に湿気が入り込みやすくなります。
特に雨が多い地域や、日当たりが悪い土地では、湿気が逃げにくくなり、シロアリにとって居心地のよい環境が生まれやすくなります。
土地選びでできる対策とは
一方で、標高が高めの場所や風通しの良いエリア、自然の少ない都市部のほうが、湿気がこもりにくく、シロアリ被害のリスクも低くなる傾向があります。
もちろん完璧に防げるわけではありませんが、土地そのものが持つ性質を活かしてリスクを減らすことができます。
土地を選ぶときには、市町村のハザードマップを確認してみるのもおすすめです。洪水や浸水の可能性があるエリアかどうかを事前に知っておくことで、より安全な土地選びができます。
家の構造や素材に気を配ることも大事ですが、最初の一歩として「どこに建てるか」はとても大切な判断材料になります。
安心して暮らせる家をつくるには、まず湿気の少ない土地からスタートすることを意識してみましょう。
よくある質問Q&A

ここでは、シロアリ対策に関してよくある疑問や不安にお答えします。家づくりを考えている方が安心して判断できるよう、できるだけわかりやすく解説していきます。
Q1.シロアリは本当に完全に防げるの?
A1.残念ながら「完全に防ぐ」ことは難しいです。自然の中に存在する生き物なので、どんなに対策をしても、100%寄せつけないという保証はありません。ただし、湿気を減らす工夫や定期的な点検、防除処理などを組み合わせることで、被害のリスクを大きく下げることは十分可能です。
定期的なメンテナンスと、環境を整えておくことがシロアリ対策の基本です。
Q2.新築でもシロアリ対策は必要?
A2.新築だからといって安心してしまうのは危険です。木材を多く使う住宅では、新しい家でも湿気や土地の条件によってシロアリが近づくことがあります。建築時に防蟻処理をしていても、年数が経てば効果が薄れるため、予防の視点は欠かせません。
家を建てたあとも、定期点検を続けていくことが大切です。
Q3.自然にいなくなることはある?
A3.シロアリは自然にいなくなることはほとんどありません。巣があれば活動を続けますし、湿気の多い環境では別の場所から新たに移ってくることもあります。一時的に姿が見えなくなっても安心せず、点検を継続することが大切です。
特に羽アリが飛び出してくる季節には、活動のサインを見逃さないよう注意しましょう。
Q4.コンクリートの家でも対策は必要?
A4.鉄筋コンクリート造の家であっても、床下や配管のまわりなど木材が使われている部分があれば、シロアリ被害の可能性はゼロではありません。また、地面との接点がある限り、どこかから侵入してくることも考えられます。
「コンクリートだから大丈夫」と思わず、必要に応じて点検や防除を取り入れるようにしましょう。
まとめ|特徴を押さえて、シロアリが来ない家づくりを

ここまで、シロアリが寄りつきにくい家をつくるための9つのポイントを紹介してきました。
ベタ基礎の採用、基礎の高さ、通気性の確保、雨漏り対策、床下構造の工夫、定期点検や予防スプレーの活用、不要物の管理、湿気の少ない土地選びなど、それぞれが大切な役割を果たします。
シロアリ被害を完全に防ぐのは難しいですが、これらの対策を組み合わせて行うことで、被害のリスクを大きく減らすことが可能です。
住宅は一度建てたら長く住み続ける場所です。だからこそ、建てる前の工夫と建てた後の管理の両方が欠かせません。
もし不安がある場合は、専門の業者や経験豊富なハウスメーカーに相談してみるのもひとつの方法です。安心して暮らせる住まいを実現するために、今できることから始めていきましょう。
最後に.
こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。
【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?
最後までお読みいただきましてありがとうございました。