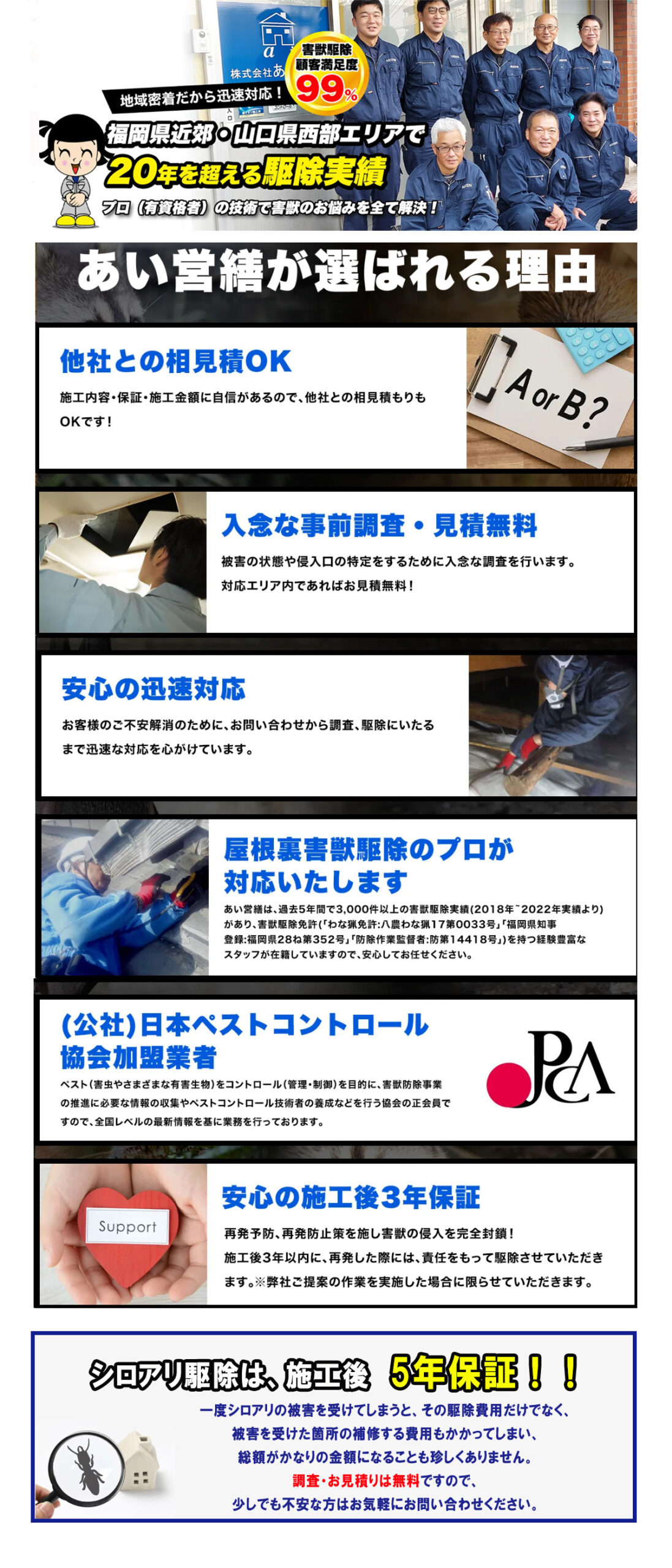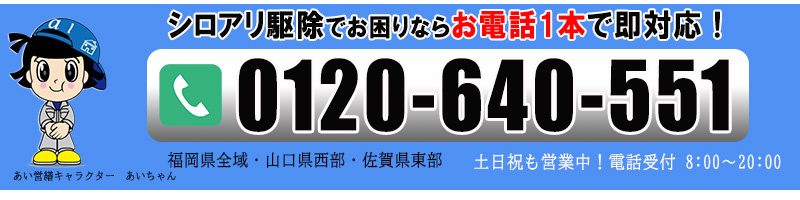シロアリは、気づかないうちに家の土台を食い荒らすやっかいな害虫です。
放っておくと、修繕費用が高額になることもあります。そこで注目したいのが「シロアリが嫌いなもの」を使った予防策です。
この記事では、専門業者に頼らずともできる、身近で手軽な対策を7つにまとめてご紹介します。早めの行動で、大切な住まいを守りましょう。
記事のポイント
● シロアリが嫌いな香りや環境について理解できる。
● 自分でできるシロアリ予防の方法がわかる。
● シロアリ対策に使える木材やベイト剤の特徴が学べる。
● 専門業者に依頼するタイミングとメリットを把握できる。
シロアリが嫌いなものとは?

家の木材をむしゃむしゃと食べてしまうシロアリ。
大切な住まいを守るためには、シロアリが「どんなものを嫌うのか」を知っておくことがとても大切です。この記事では、まずシロアリが嫌いな要素についてわかりやすくご紹介します。
シロアリが苦手とするもの
シロアリが嫌いなものには、いくつか共通した特徴があります。
主に「香り」「乾燥」「光」など、シロアリの生態に関係する要素が多く見られます
例えば、ハッカやシナモンのような強い香り、風通しが良く乾いた場所、太陽の光がよく当たるところなどは、シロアリにとって居心地が悪い環境になります。
また、ヒバやヒノキ、スギといった天然の防虫成分を含む木材や、シロアリの巣にまで効果が及ぶベイト剤と呼ばれる駆除アイテムも、シロアリが避けたがる存在です。
こういった特徴は、シロアリの生活スタイルに深く関係しています。シロアリは基本的に湿気のある暗い場所を好み、乾燥や日差しを避けながら移動します。
鼻が利く昆虫でもあるため、強い匂いも嫌がる傾向にあるのです。
今回紹介する「シロアリが嫌いなもの7選」
シロアリ対策をする上で、自分でも簡単に取り入れられる方法があるとうれしいですよね。ここからの記事では、シロアリが嫌がるものを使った対策を7つに厳選してご紹介していきます。
具体的には、次のような内容を扱います。
-
ハッカの香りを使った予防方法
-
シナモンの活用法
-
ヒバやヒノキなどの木材の特徴
-
光や乾燥を利用した環境づくり
-
ベイト剤を使った駆除方法
-
段ボールや木材を放置しない工夫
-
専門業者への相談のタイミング
どれも特別な道具や知識がなくても実践できるものばかりです。自宅を守る第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。次の章から、それぞれの対策を詳しく見ていきましょう。
1. ハッカの香りでシロアリを遠ざける

シロアリが嫌う香りのひとつに「ハッカ」があります。
ハッカはスーッとした清涼感のある香りが特徴で、虫よけとしてもよく知られています。この香りにはメントールという成分が含まれていて、多くの虫が苦手としています。
シロアリも例外ではなく、ハッカの香りを避けようとする傾向があるのです。
特に夏場はシロアリの活動が活発になる時期ですので、ハッカを使った対策は効果的といえるでしょう。
しかも、ハッカは家庭でも簡単に取り入れられる方法が多いため、気軽に始められるのも魅力のひとつです。
ハッカ油スプレーを作ってみよう
ハッカの香りを手軽に活用する方法のひとつが、ハッカ油スプレーです。
市販でも購入できますが、自宅で作ることもできます。材料はハッカ油と無水エタノール、水の3つだけです。エタノールにハッカ油を数滴垂らし、そこに水を加えてスプレーボトルに入れれば完成です。
このスプレーをシロアリが侵入しやすい場所、例えば家の基礎周りや換気口の近く、段ボールや木材のそばなどに吹きかけておくと予防になります。
ただし、香りは時間が経つと薄れてしまうため、定期的に使い直すことが大切です。
また、ハッカ油は人には心地よい香りでも、ペットには強すぎることがあります。犬や猫がいる家庭では、使用する場所を工夫したり、少量ずつ使ったりするように気をつけましょう。
ハッカの鉢植えにも注意点がある
ハッカは繁殖力の高い植物としても知られており、初心者でも育てやすいのが特徴です。
庭やベランダで鉢に植えておくことで、シロアリ対策として活用できます。ただし、ここでひとつ注意点があります。
ハッカは地植えにすると広がりすぎて他の植物を押しのけてしまうことがあります。
さらに、鉢をたくさん置きすぎると湿気がこもり、逆にシロアリが好む環境をつくってしまうことも。植える場合は鉢を使い、日当たりの良い場所に控えめに配置するのがポイントです。
手軽でナチュラルなシロアリ対策としてハッカはとても優秀です。ただし、使い方を間違えると逆効果になることもあるので、正しく取り入れて家を守っていきましょう。
2. シナモンで自然な防虫対策

シロアリ対策と聞くと、強力な薬剤を使うイメージを持つ人も多いかもしれませんが、実はシナモンのような身近な香りでも効果が期待できます。
料理やお菓子作りでおなじみのスパイスですが、その香りにはシロアリが嫌がる成分が含まれているのです。
シナモンの中には「オイゲノール」や「シナムアルデヒド」という成分があり、これが防虫に役立ちます。
市販の防虫スプレーにも使われていることがあるほどで、シロアリもこの独特な香りを避ける傾向があります。
シナモンの使い方はいろいろあります
シナモンを使ったシロアリ対策には、いくつかの方法があります。
まず手軽なのはシナモンパウダーです。木材の接合部や床下の隙間、外壁と基礎の境目など、シロアリが通りそうな場所に振りかけて使います。見た目が気になる場所は、少量ずつ使うとよいでしょう。
もう少し広範囲に使いたい場合は、シナモンスプレーがおすすめです。水にシナモンパウダーを混ぜて加熱し、冷ましてからスプレーボトルに移すだけで作れます。
庭先や基礎の周囲、ウッドデッキなどに吹きかければ、香りでシロアリを遠ざけることができます。
さらに、シナモンオイルを使う方法もあります。これは特に香りが強いため、木のつなぎ目や隙間に綿棒などで塗ると、ピンポイントで対策できます。
持続力があるため、定期的に塗り直すだけである程度の効果が期待できます。
小さな子供やペットがいる家庭では注意も必要
自然由来の素材とはいえ、使い方によっては注意が必要です。
たとえば、小さなお子さんやペットがいる家庭では、シナモンのパウダーやオイルを口に入れてしまうリスクもあります。
特に犬や猫は嗅覚が非常に敏感なので、強い香りにストレスを感じてしまうこともあります。屋内で使用する際は子どもやペットが触れない場所に限定したり、外周りのみに使ったりするなど、工夫が大切です。
シナモンは、身近で手に入りやすく、香りも良いため、無理なく始められる自然派のシロアリ対策として人気があります。
強い薬剤を使いたくない方にはぴったりの方法ですが、過信せず、他の対策と組み合わせて使うのがポイントです。
3. ヒバ・ヒノキ・スギなどの木材

シロアリは木を好んで食べますが、すべての木材が同じように狙われるわけではありません。
実は、シロアリが嫌がる成分を含んだ木もあるのです。
特にヒバやヒノキ、スギといった日本で古くから使われている木材には、防虫効果があるとされています。これらの木材を活用することで、家そのものがシロアリ対策になる可能性もあるのです。
天然の防虫成分を持つ木材の特徴
ヒバやヒノキには、「ヒノキチオール」という成分が含まれており、この成分が虫を遠ざける働きをします。
実際に、防虫剤の原料としても使われるほど効果がある成分です。スギにも似たような香り成分が含まれていて、シロアリが近づきにくくなります。
こうした木材は香りが強く、湿気にも強いという特徴があるため、昔から神社仏閣や伝統的な家屋の建材として重宝されてきました。
木の中でも硬さや水分の含み具合によってもシロアリの好みが分かれるため、防虫効果のある木材は非常に理にかなっているといえます。
建材としての活用と注意点
ヒバやヒノキ、スギなどの木材は、住宅の柱や土台、床材などに使うと効果的です。とくに青森ヒバは防虫性が高く、腐りにくいことから人気があります。
新築やリフォームの際に、これらの木材を部分的にでも取り入れることで、シロアリの被害を受けにくい家づくりができます。
ただし、どんなに防虫成分を含んでいても「絶対に食べられない木」というわけではありません。
シロアリは飢えればどんな木でもかじってしまいますし、加工の過程で高温乾燥させることで防虫成分が薄れてしまう場合もあります。
また、木の中心部(心材)は比較的強いですが、外側(辺材)は弱く、被害にあうこともあります。
つまり、ヒバやヒノキだからといって油断は禁物です。あくまでも「予防効果がある」という位置づけで考え、他の対策と組み合わせることが大切です。
木材選びとあわせて、湿気をためない工夫や定期的な点検を忘れずに行うことで、シロアリから家をしっかり守ることができます。
4. 光と乾燥した環境をつくる

シロアリは、じめじめした暗い場所を好む生き物です。
自然界では倒木や湿った地面の下などで生活しており、光や乾燥にはとても弱いという特徴があります。
これを逆手に取って、住まいの環境を「シロアリにとって居心地の悪い場所」に変えることが、効果的な予防策につながります。
湿気と暗さがシロアリを呼び寄せる
家の中でも特に注意が必要なのが、風通しの悪い場所や日が当たりにくい場所です。
たとえば床下や押し入れ、家具の裏側などは、湿気がこもりやすく、シロアリにとっては快適な空間になってしまいます。こうした場所では、シロアリが見つかる前から対策をしておくことが大切です。
また、シロアリは紫外線にも弱いため、日当たりの良い環境を作ることも予防効果があります。
光が差し込む場所では、シロアリはなかなか活動できません。庭木の剪定をして光を入れたり、室内のカーテンを開ける習慣をつけたりすることも、小さな予防につながります。
家全体の湿気を減らすためにできること
シロアリ対策として湿気をコントロールすることはとても重要です。
まずは排水環境を整えること。雨どいや排水溝が詰まっていないかをチェックし、水たまりができないようにしましょう。
また、除湿機を使って室内の湿度を下げるのも効果的です。特に梅雨や雨の多い季節は、湿度が上がりやすいため注意が必要です。
床下の換気口にも注目しましょう。換気口の前に物を置いてしまっていると空気の流れが悪くなり、湿気がこもってしまいます。定期的に点検し、風通しの良い状態を保つことが大切です。
湿気をためない、明るく風通しの良い住まいは、シロアリだけでなくカビやダニの予防にもつながります。日々のちょっとした工夫で、シロアリが近寄りにくい家づくりを進めていきましょう。
5. ベイト剤で巣ごと駆除
シロアリ対策の中でも、根本的な解決を目指すなら「ベイト剤」の活用がおすすめです
ベイト剤とは、シロアリにとってのエサに見せかけた毒餌のことで、巣にいる仲間ごと退治することが目的です。
薬剤と聞くと心配になる方もいるかもしれませんが、使い方を守れば人やペットにもやさしい方法です。
ベイト剤の仕組みと使い方のコツ
ベイト剤の中には「脱皮阻害剤」と呼ばれる成分が入っています。
これは、シロアリの成長を妨げるもので、食べたシロアリが自分の巣に戻り、仲間にも分け与えることで巣全体に効果が広がります。
時間をかけてじわじわと効いていくため、即効性はありませんが、最終的には巣ごと壊滅させることが可能です。
また、脱皮阻害剤は昆虫にしか作用しないため、哺乳類である人間や犬・猫には影響がほとんどないとされています。
しかも、ベイト剤は地面の中に設置するため、小さなお子さんやペットが誤って触れる心配も少なく、安全性の面でも安心できます。
設置場所と種類に応じた注意点
ベイト剤は、シロアリが通りやすい場所に設置するのがポイントです
家の周囲の土に埋めるタイプが一般的で、目立ちにくく、屋外でも使いやすいです。ただし、どこに置けば効果的か分からない場合は、被害が疑われる場所や湿気の多い場所を優先しましょう。
シロアリの種類によっても、必要なベイト剤の数が変わります。
例えば、日本でよく見られるヤマトシロアリは巣の規模が比較的小さく、数か所に設置すれば十分なことが多いです。
一方で、イエシロアリは大量に巣を作る性質があり、より多くの設置ポイントが必要になります。種類が分からない場合は、早めに専門業者に相談すると安心です。
ベイト剤は、手軽で効果的なシロアリ対策のひとつです。ただし、効果が出るまでには時間がかかるため、すぐに結果を求めるよりも、長期的な視点でじっくりと巣を狙う方法と考えるとよいでしょう。
6. 木材や段ボールを放置しない
シロアリは、湿った木材や紙類が大好物です。
とくに、雨や湿気を吸い込んだ段ボールや使いかけの木材は、シロアリにとっては格好のエサになります。家の周りにこれらを放置しておくと、いつの間にかシロアリを呼び寄せてしまう原因になってしまいます。
放置された物がシロアリの入口になる
引っ越し後の段ボールやDIYで余った木材を、つい庭やベランダの隅に置きっぱなしにしていませんか?
見た目には問題がないように思えても、長く放置することで湿気を含み、シロアリが寄りつく環境を作ってしまいます。
特に地面に直接置かれた段ボールは、湿気を吸いやすく分解されやすいので注意が必要です。
また、古い木材も放置しておくと、シロアリが中に入り込んで巣を作るリスクも高まります。使わないものはできるだけ早く処分しましょう。
防腐処理で被害を予防する
もしどうしても屋外に木材を保管する必要がある場合は、防腐処理を施しておくと安心です。
市販の防腐剤を塗るだけでも、シロアリの被害を抑える効果があります。また、地面に直接置かず、すのこやブロックを使って風通しを確保する工夫も効果的です。
小さなことのように思えても、湿った段ボールや木材はシロアリにとっては絶好のチャンスです。
家の周りを定期的にチェックし、不用なものは早めに片づけるようにしましょう。これだけでも、シロアリ対策としては大きな一歩になります。
7. 専門業者による点検・駆除

これまで紹介してきた対策は、いずれも自分でできる予防や応急処置として有効ですが、すでにシロアリの被害が出ている場合や、確実に家を守りたいというときは、専門業者による点検や駆除が最も確実な方法です。
プロの手による対策は、効果の持続性や施工の丁寧さの面で大きな違いがあります。
自力での対策とプロによる駆除の違い
市販の薬剤や自然素材を使った方法は手軽ですが、どうしても「表面的な対策」にとどまりがちです。
一方、専門業者はシロアリの習性や被害状況を把握した上で、的確に対処してくれます。被害箇所の見極めから、土壌処理や建物全体の保護処置までを一貫して行ってくれるため、再発のリスクもぐっと減らせます。
また、シロアリは目に見えない場所に巣を作ることが多く、被害が進んでからでは修復費用も高くついてしまいます。早めにプロに相談することで、結果的に費用や手間を抑えることができます。
相見積もりと無料点検を上手に活用する
専門業者に依頼する場合でも、費用が気になるという方も多いかと思います。
そんなときにおすすめなのが「相見積もり」です。複数の業者に見積もりを依頼することで、価格の相場がわかり、不当に高い料金を回避することができます。
さらに、最近では無料点検を実施している業者も増えており、気になる箇所だけを見てもらうだけでもOKというところもあります。
点検だけならリスクも少なく、まずは現状を把握するだけでも大きな安心につながります。
被害が広がる前に、一度プロの目でチェックしてもらうことを検討してみましょう。自分での対策と組み合わせることで、より安心な住まいを維持することができます。
福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の
「シロアリ駆除」ならお電話1本で駆け付けます!
公益社団法人日本しろあり対策協会会員
0120-640-551
まとめ:シロアリ対策は早めの行動がカギ

今回は「シロアリが嫌いなものと対策7選」というテーマで、家庭でできる予防策から専門業者に依頼する方法までを幅広くご紹介しました。
振り返ると、シロアリが苦手とするものには、ハッカやシナモンの香り、乾燥や光、特定の木材、ベイト剤などがありました。加えて、段ボールや木材を放置しない、定期的に業者に点検してもらうことも重要な対策です。
こうした方法は、すぐに始められる身近なものが多いため、「自分でできる予防」として取り入れやすいのが魅力です。
一方で、すでに被害が出ている場合や、広範囲に及んでいると感じたら、迷わず専門業者に相談することをおすすめします。
大切なのは「様子見」ではなく、「早めの対応」です。シロアリの被害は放っておくと家の構造にまで影響し、修繕費用も高くついてしまいます。
今回紹介した内容を参考に、できることから少しずつ始めて、大切な住まいをシロアリから守っていきましょう。
最後に.
こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。
【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?
最後までお読みいただきましてありがとうございました。