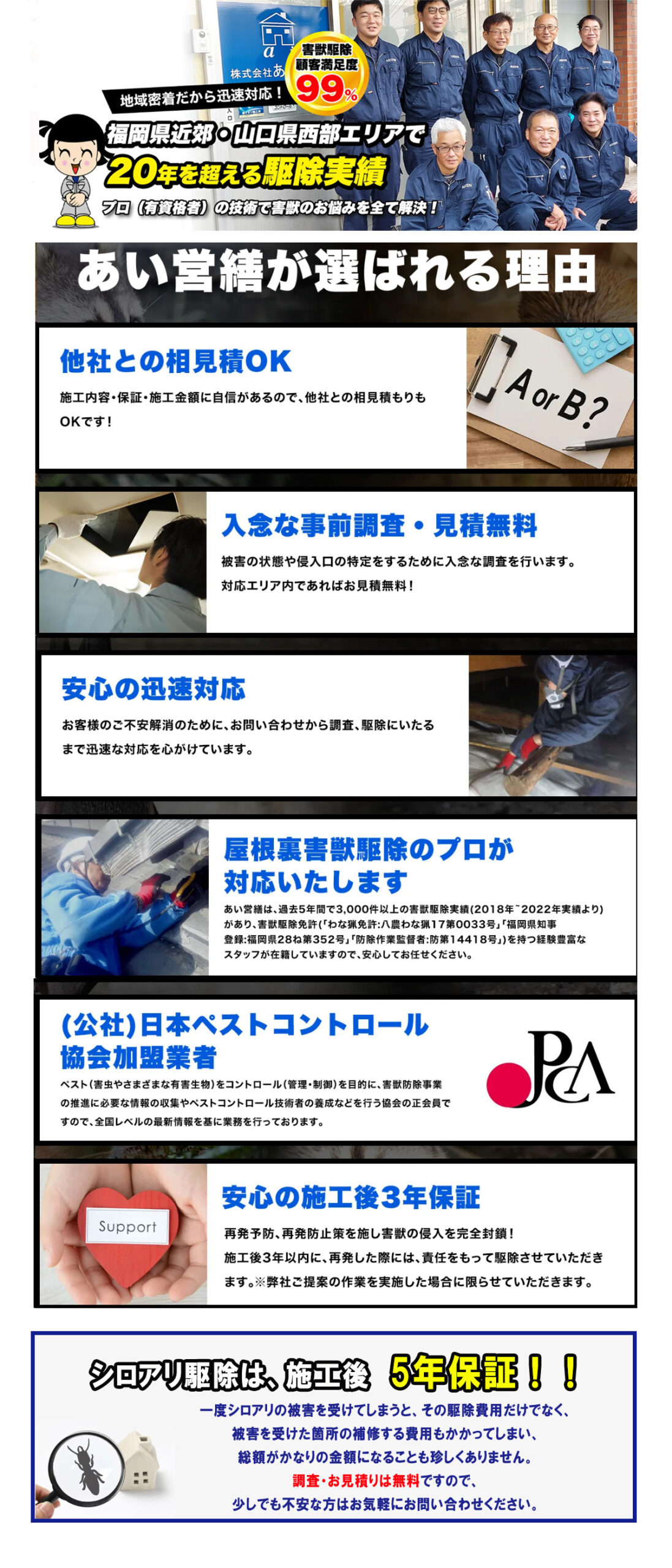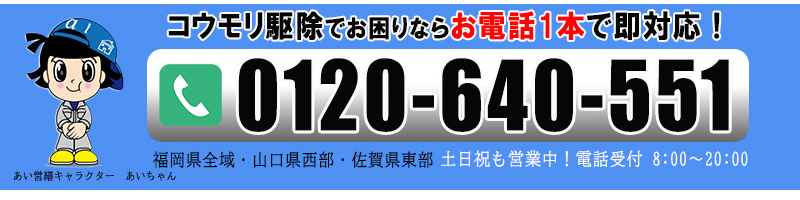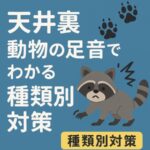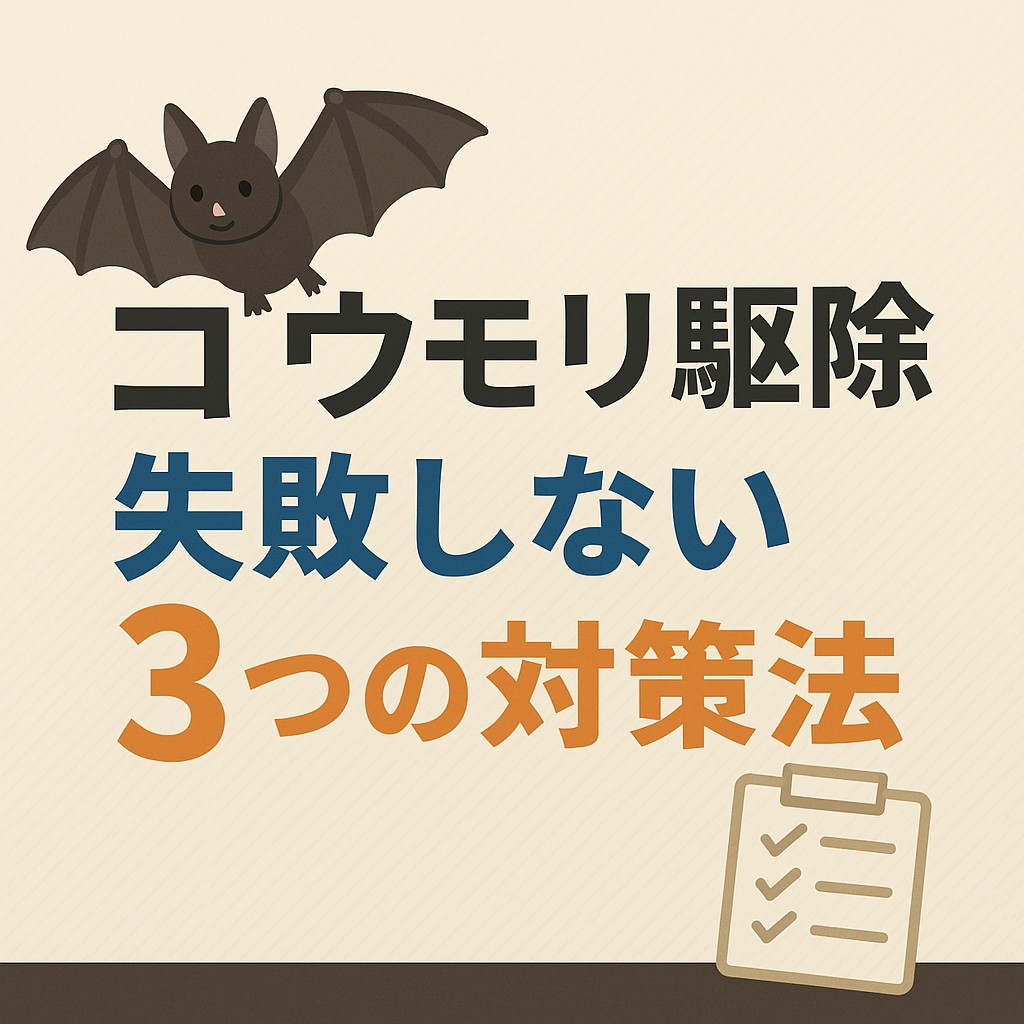
近年、コウモリが家屋に住みつく被害が全国で増加しています。
屋根裏や換気口、シャッターの隙間など、わずかなスペースを見つけて住みつくため、一度入り込まれると追い出すのが厄介です。
さらに、放置すれば糞尿による悪臭や壁材の腐食、ダニの発生といった深刻な被害につながることもあります。
こうした事態を受けて、「自分で駆除しよう」と考える方も多いのですが、実はそれがかえって逆効果になるケースもあります。
タイミングを間違えると、コウモリが屋内に閉じ込められ、暴れて被害を悪化させることがありますし、法律に違反してしまう可能性もあるのです。
そこでこの記事では、コウモリ駆除で失敗しないために必要な3つの対策法をわかりやすくご紹介します。
自力で対応したい方も、業者に相談するか迷っている方も、まずは「正しい順序と知識」を身につけることが、失敗を防ぐ一番のポイントです。
今後の被害を未然に防ぐためにも、ぜひ参考にしてみてください。
記事のポイント
●コウモリ駆除の基本的な3つの対策方法がわかる。
●侵入口の特定と封鎖に必要なポイントが理解できる。
●フンやダニによる衛生被害と清掃方法が学べる。
●法律に違反しないための注意点と業者依頼の重要性がわかる。
コウモリ駆除は“正しく”行わないと逆効果

近年、コウモリが家屋に住みつく被害が全国で増加しています。
屋根裏や換気口、シャッターの隙間など、わずかなスペースを見つけて住みつくため、一度入り込まれると追い出すのが厄介です。
さらに、放置すれば糞尿による悪臭や壁材の腐食、ダニの発生といった深刻な被害につながることもあります。
こうした事態を受けて、「自分で駆除しよう」と考える方も多いのですが、実はそれがかえって逆効果になるケースもあります。
タイミングを間違えると、コウモリが屋内に閉じ込められ、暴れて被害を悪化させることがありますし、法律に違反してしまう可能性もあるのです。
そこでこの記事では、コウモリ駆除で失敗しないために必要な3つの対策法をわかりやすくご紹介します。
自力で対応したい方も、業者に相談するか迷っている方も、まずは「正しい順序と知識」を身につけることが、失敗を防ぐ一番のポイントです。
今後の被害を未然に防ぐためにも、ぜひ参考にしてみてください。
対策①:まずは追い出し!効果的なアイテムと使い方

コウモリ駆除の第一歩は「追い出し」です。いきなり封鎖してしまうと、コウモリが屋根裏や壁の中に閉じ込められてしまい、死骸や糞尿がたまって二次被害の原因になります。
まずは、コウモリが自分から出ていくような環境をつくることが大切です。ここでは、コウモリが嫌がるニオイや光、音を使った具体的な方法と、注意すべきポイントを解説します。
コウモリが嫌うニオイと音・光
コウモリは嗅覚や聴覚が非常に敏感な動物です。そのため、刺激の強いニオイや不快な音、光などを使えば、居心地の悪さを感じて自然と出ていってくれる可能性があります。
まずおすすめなのがハッカ油です。清涼感のある香りで人には気持ちよく感じることもありますが、コウモリにとっては刺激が強すぎるため、避けるようになります。
水に薄めてスプレーにすることで、屋根裏や換気口付近に簡単に散布できます。
次に効果があるのが木酢液。こちらはやや焦げ臭いような独特のにおいがあり、コウモリが嫌がるニオイのひとつとして知られています。
市販の木酢液も手に入りやすく、スプレーや染み込ませた布などで使うのが一般的です。
また、超音波装置も有効です。人には聞こえにくい高周波音を発することで、コウモリにとってストレスとなる環境をつくります。
さらに、点滅ライトや青色LEDなどの強い光もコウモリは苦手です。夜間に光を当てることで、安眠の邪魔をされることになり、巣を離れる原因になります。
これらを複数組み合わせることで、より高い追い出し効果を得ることができます。
使用するタイミングと注意点
効果的に追い出しを行うには、タイミングがとても重要です。
コウモリは夜行性なので、日没直後が最も外に出る時間帯です。このタイミングに合わせて超音波装置やライトを作動させたり、ニオイを散布することで、屋内に残った個体を減らしやすくなります。
注意したいのは、「まだ中にコウモリが残っているうちに侵入口をふさいでしまうこと」です。
中に閉じ込められたコウモリはパニックを起こして飛び回ったり、別のすき間をこじ開けて屋内に侵入してきたりする危険があります。
さらに、逃げられなくなったコウモリがその場で死んでしまうと、死骸からの腐敗臭や害虫の発生にもつながってしまいます。
そのため、確実に外に出たことを確認してから封鎖作業に入ることが大切です。夜に追い出しをして、翌朝に確認するなど、時間差をつけると安心です。
コウモリの追い出しは、最初のステップでありながら非常に重要な工程です。
焦って封鎖せず、まずは「ここはもう居心地が悪い」と感じさせる工夫をじっくり行うことが、失敗しない駆除への第一歩です。
次の章では、その追い出し後に行うべき「侵入経路の封鎖」について詳しくご紹介します。
対策②:侵入口を完全に封鎖する

コウモリの追い出しに成功したとしても、根本的な解決にはなりません。
肝心なのは、再び同じ場所に戻ってこられないようにする「侵入口の封鎖」です。コウモリはとても小さなすき間からも入り込むため、1ヶ所でも見逃すと再発してしまいます。
この章では、コウモリが侵入しやすい場所のチェックポイントと、封鎖に適した資材や施工のコツをご紹介します。
侵入しやすい場所とチェックリスト
コウモリは体が柔らかく、5mm程度のすき間があれば簡単に通り抜けてしまいます。そのため、「こんな小さな穴から?」と思うような場所でも要注意です。以下のような場所を重点的にチェックしましょう。
-
屋根裏のすき間:屋根材の重なり部分や軒下などにすき間ができやすいです。
-
換気口や通気口:外壁や天井に設けられている換気設備の周辺は、カバーが劣化していることも。
-
エアコンや給湯器の配管まわり:パテやテープが劣化していると、そこから入り込まれることがあります。
-
雨戸・シャッターの収納部:暗くて静かなスペースは、コウモリにとって居心地のよい場所です。
-
屋根の隙間や破損部分:台風や経年劣化でできた穴も侵入経路になりやすいです。
これらのポイントをひとつひとつ確認していくことが、再侵入を防ぐための第一歩です。
封鎖に適した資材と施工ポイント
侵入口が特定できたら、次は封鎖作業です。大切なのは、壊されにくく、噛み破られにくい資材を使うこと。おすすめの素材は以下の通りです。
-
パンチングメタル(穴あき金属板):通気性を保ちながら、しっかりと物理的に遮断できます。主に換気口などに使用されます。
-
ステンレス製の金網:柔軟に形を変えられるため、屋根や配管周りなどの複雑な形状にも対応可能です。
-
シーリング材(防水コーキング):小さな穴やすき間を完全にふさぐのに適しています。外壁のヒビや配管まわりなどに使用します。
施工の際には、単にかぶせるだけでなく、ビスや針金でしっかり固定することが大切です。粘着テープや柔らかい素材だと、コウモリに押し破られる可能性があります。
また、風雨にさらされる場所には防水性能のある素材を選ぶようにしましょう。
もし自分で施工するのが難しい場合や、高所作業を伴う場所であれば、無理をせず業者に相談するのが安全です。
特に屋根や天井裏は足場が不安定になりやすく、ケガのリスクも高いため注意が必要です。
侵入口の封鎖は、駆除の中でも最も重要な工程です。ここがしっかりできていないと、どんなに追い出しても意味がありません。
「入れない環境」を作ることが、コウモリ被害から解放されるための一番の近道です。次の章では、最後の仕上げとなる「清掃と消毒」についてお伝えします。
対策③:フン・臭い・ダニの清掃と消毒

コウモリを追い出し、侵入口をしっかり封鎖できたとしても、まだ安心してはいけません。
彼らが住みついていた場所には、フンや尿、ダニなどの痕跡が大量に残っています。これを放置すると、悪臭や建物の腐食、さらには健康被害につながる恐れがあるため、必ず「清掃」と「消毒」を行う必要があります。
この章では、清掃を怠ることで起きるリスクと、安全に作業を進める方法について解説します。
放置すると起きる衛生リスク
コウモリのフンは、見た目には小さくても侮れません。
長期間ためこまれることで、強い悪臭を放つようになり、天井や壁材にも染み込んでしまいます。その結果、建材の腐食やカビの原因になり、住宅の劣化を早める恐れがあります。
また、フンや巣の周辺には「ヒストプラズマ菌」と呼ばれるカビの一種が存在することがあります。
これは、空気中に舞い上がった胞子を吸い込むことで肺に感染し、ヒストプラズマ症という病気を引き起こすことがあります。
症状としては咳や発熱、肺炎のような状態になることがあり、免疫力の低い人や高齢者にとっては深刻です。
さらに、コウモリの体や巣にはダニやノミが寄生していることが多く、駆除後にそれらが人の生活空間に広がってしまうこともあります。
皮膚炎やかゆみなどの原因となり、見えないストレスにつながることも少なくありません。
安全に清掃・消毒する方法
清掃を行う際には、まずしっかりと準備をすることが大切です。最低限、以下の道具を用意しましょう。
-
ゴム手袋(使い捨てタイプがおすすめ)
-
マスク(防塵・抗菌フィルター付きが望ましい)
-
ゴーグルまたはメガネ
-
雑巾や使い捨ての布
-
ごみ袋(二重にして処理)
-
市販の消毒スプレー(アルコールや次亜塩素酸系)
作業の手順としては、まず乾いたフンを慎重に取り除きます。この時、ホコリが舞わないようにゆっくり作業するのがポイントです。
次に、消毒スプレーを吹きかけて除菌・消臭を行います。壁や断熱材などにしみ込んでいる場合は、表面だけでなく内部にもスプレーを浸透させるようにしましょう。
ただし、広範囲にわたる汚染や、屋根裏など狭くて作業がしにくい場所の場合は、無理に自分で対応せず専門業者に任せる判断も大切です。
業者であれば、専用の消毒薬や防虫処理までセットで行ってくれるため、衛生面でも安心ですし、再侵入を防ぐ効果も期待できます。
清掃と消毒は、駆除後の“仕上げ”ともいえる大切な工程です。この作業を丁寧に行うかどうかで、快適な生活が戻るスピードも変わってきます。
見えない部分だからこそ、しっかりと対策することが、失敗しないコウモリ駆除への最終ステップなのです。次の章では、法律や業者依頼の必要性についてご紹介します。
法律に注意!駆除に許可は必要?
コウモリを見つけたとき、「すぐに捕まえて外に出そう」と考える方は少なくありません。
しかし実は、コウモリは日本の法律で守られている動物であり、間違った対処をすると法令違反となってしまう恐れがあります。
ここでは、コウモリ駆除に関する法律の基本と、安全に対応するためのポイントをご紹介します。
鳥獣保護管理法の概要
日本では「鳥獣保護管理法」という法律によって、野生動物の多くが保護されています。
コウモリもこの法律の対象となっており、許可なく捕獲・殺傷することは禁止されています。つまり、「罠を仕掛けて捕まえる」「毒で駆除する」といった行為は、個人の判断では行ってはいけないのです。
たとえ自宅での被害であっても、無許可での捕獲や殺処分を行うと、処罰の対象になる可能性があります。
知らずにやってしまったとしても、「知らなかった」では済まされない場合もありますので、注意が必要です。
違反リスクを避けるための対策
では、どう対応すればよいのでしょうか。
実は、コウモリを「追い出す」「侵入口をふさぐ」といった行為は問題ありません。法律が規制しているのはあくまで「捕獲・殺傷」であって、コウモリが自然に出ていくように仕向ける方法は合法です。
そのため、これまで紹介してきたようなハッカ油や超音波を使った追い出しや、金網などでの封鎖といった対策は、自分で行っても大丈夫です。
ただし、封鎖を行う際には、中にまだコウモリが残っていないかをよく確認してから作業しましょう。閉じ込めてしまうと、結局「殺してしまう」ことになりかねず、法律にふれる可能性があります。
より確実に、かつ安全に対策したい場合は、専門の駆除業者に依頼するのが最も安心です。
業者は法律に沿った手続きや手法で対応してくれるため、自分で行うよりもリスクを大きく減らすことができます。許可の取得が必要な場合も、代行してくれる業者が多く存在します。
コウモリ駆除には、正しい知識と法的な配慮が不可欠です。
「よかれと思ってやったこと」が違法になるリスクを避けるためにも、ルールを守った方法での対応を心がけましょう。次は、記事のまとめとして、3つの対策を整理してご紹介します。
まとめ:正しい3ステップで安心・安全な駆除を
コウモリ駆除で大切なのは、焦らず、正しい手順で確実に対処することです。
コウモリは見た目の被害だけでなく、健康面や家屋へのダメージ、さらには法的リスクにもつながる可能性があるため、自己流での対応は思わぬ落とし穴にはまることもあります。
本記事で紹介したように、まずは「追い出し」でコウモリに居心地の悪さを感じさせ、自然に出ていってもらう。
そして、再侵入を防ぐために「封鎖」を徹底し、最後に「清掃と消毒」で健康リスクを取り除く。この3ステップを丁寧に行うことが、失敗しないための基本です。
また、法律のルールに従いながら、安全かつ確実に対応するためには、状況によっては専門の業者に相談するのが賢明です。早めに行動すれば被害は小さく済み、費用も抑えられる可能性があります。
「コウモリを見かけたけど、どうしたらいいのかわからない」──そんな方は、まずは今回の3つの対策を参考に、無理のない範囲で行動を始めてみてください。
正しい知識と対応で、安心できる住まいを取り戻しましょう。
最後に.
こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。
【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
最後に.
こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。
【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?
最後までお読みいただきましてありがとうございました。