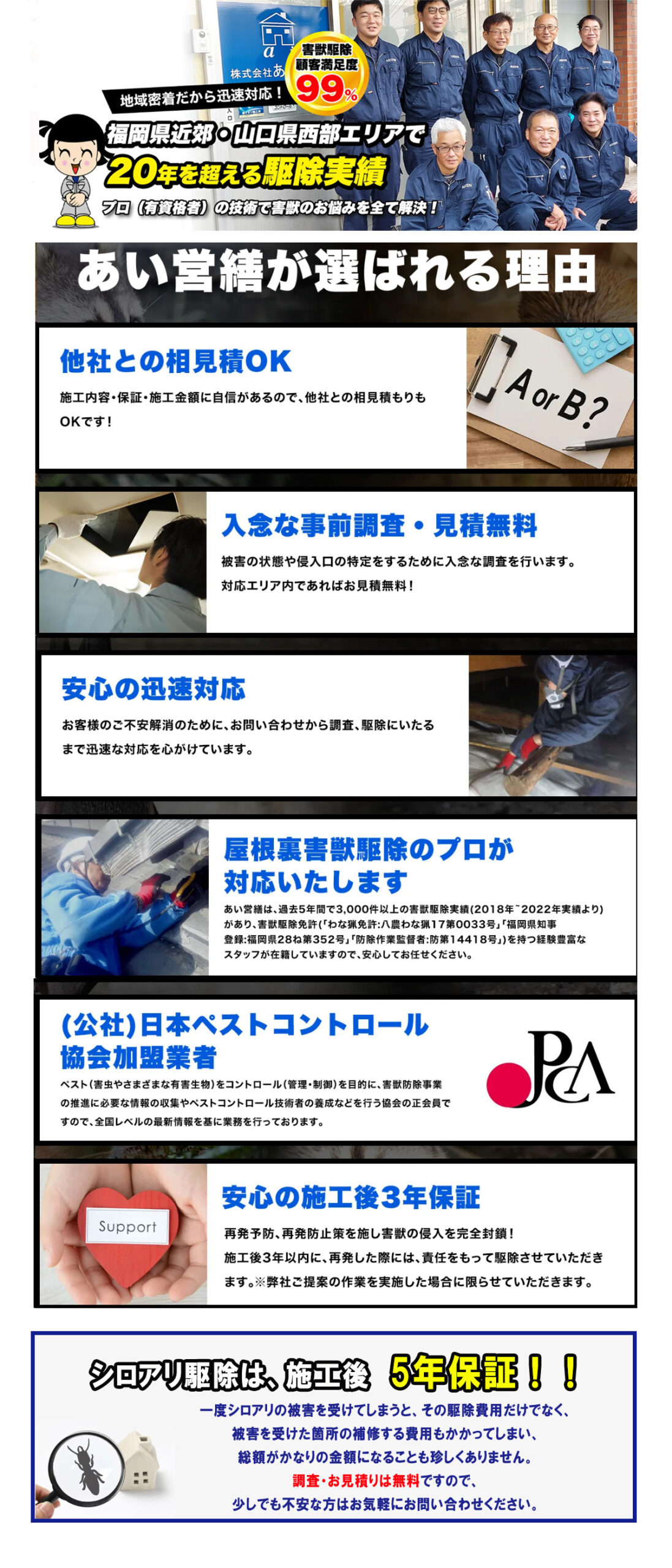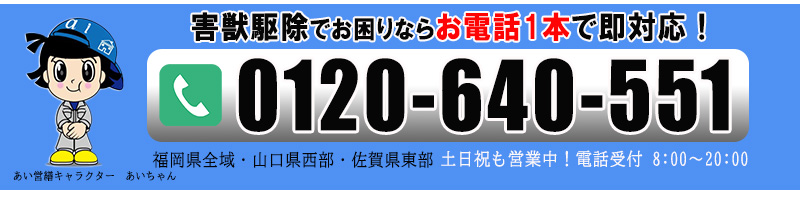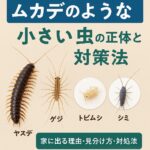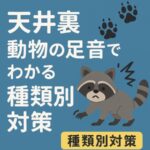夜中に天井裏からバタバタと音がする…。
畑の果物が毎年荒らされてしまう…。
そんな経験をしたことがある方は、もしかするとハクビシンの被害に遭っているかもしれません。
ハクビシンは一見かわいらしい見た目をしていますが、実際にはとても厄介な害獣です。屋根裏に住みつかれると、騒音や悪臭だけでなく、糞尿による建物の腐食やアレルギーの原因にもなります。
また、畑や家庭菜園では果物や野菜が食い荒らされるなど、農作物への被害も少なくありません。
被害に気づいても、いきなり業者に依頼するのはちょっとハードルが高い…と感じる方も多いのではないでしょうか?
そこでこの記事では、家庭でもできるハクビシン対策を中心に、再発を防ぐためのポイントや、知らないと損する法律上の注意点まで、実践的な情報をわかりやすく解説します。
大切なのは、「放っておかないこと」と「正しい知識を持つこと」。
この記事を通して、ご自宅の安全を守るための第一歩を踏み出していただけたらと思います。
記事のポイント
●ハクビシンの習性や被害の特徴が理解できる。
●家庭でできる具体的なハクビシン対策がわかる。
●フンの処理や消毒の重要性と方法が学べる。
●法律に違反しない正しい駆除の手順が理解できる。
ハクビシンの習性と行動パターンを知ろう

ハクビシン対策を成功させるためには、まず相手の習性を知ることが大切です。
「どんな時間に動いているのか」「どこに潜んでいるのか」「何が苦手なのか」など、ハクビシンの生活スタイルを理解することで、より効果的な対策ができるようになります。
ハクビシンは夜行性!昼間はどこに?
ハクビシンは基本的に夜行性の動物です。
夕方から夜にかけて活動を始め、餌を求めて人家の周辺や農地を徘徊します。特に果物や野菜、残飯などに引き寄せられやすく、人が寝静まった頃に屋根裏に侵入するケースが多いです。
日中はどうしているのかというと、暗くて静かな場所にじっと潜んでいます。代表的なのが以下のような場所です。
-
屋根裏や天井裏
-
納屋や物置の中
-
樹木の茂みや庭の隅
-
床下や壁の隙間
多くの方が「夜になると天井裏でドタドタ音がする」と感じるのは、まさにこの行動パターンによるものです。
足音の正体がわからず不安になり、朝になると静かになるので見失ってしまうという方も少なくありません。
また、ハクビシンは一定の場所にフンをする「ためフン」の習性があるため、屋根裏や畑に特定の場所で異臭を感じたら、侵入している可能性が高いといえます。
何が苦手?ハクビシンが嫌うもの
ハクビシンの習性を活かすには、「嫌うもの」を利用して近寄らせない工夫が重要です。ハクビシンが特に苦手とするのは、以下の3つです。
1. 光(ライト)
ハクビシンは暗い場所を好むため、強い光や点滅するライトが苦手です。
センサー付きのライトを屋根裏の入り口や庭先に設置することで、驚かせて近寄らせない効果があります。
-
太陽光で充電できるソーラー式の防獣ライトが便利
-
点滅するライトはより高い忌避効果が期待できる
2. 音(超音波)
人間には聞こえにくい高周波の超音波も、ハクビシンには不快な音として届きます。
最近では、周波数が変化するタイプやモーションセンサー付きのものなど、ハクビシン専用の超音波機器も多く販売されています。
-
動きを感知して音が出る機種は省エネかつ効果的
-
設置場所はハクビシンの通り道や出入口付近がおすすめ
3. におい(木酢液・ハッカ油)
強い刺激臭もハクビシンの天敵です。特に木酢液やハッカ油のにおいは、ハクビシンが本能的に避けるとされています。
-
木酢液は布に染み込ませて吊るしたり、スプレーで散布する
-
ハッカ油はアルコールや水で薄めてスプレーにすると使いやすい
-
雨や時間の経過で効果が薄れるので、こまめな再施工が必要
これらの「ハクビシンが嫌う要素」を組み合わせて使うことで、居心地の悪い環境をつくり、自然と遠ざけることができます。
次の章では、これらの習性を踏まえて、実際にどんなグッズや対策法を使えばいいのか、具体的に紹介していきます。ご家庭でもすぐに取り入れられるものばかりなので、ぜひ参考にしてください。
自宅や畑でもできる!実践的なハクビシン対策

ハクビシンの被害に悩んでいる方の多くは、「業者に頼む前に、自分でなんとかできないか?」と考えているのではないでしょうか。
実は、自宅や畑でもできるハクビシン対策はたくさんあります。最近ではホームセンターやネット通販でも手軽に対策グッズが手に入るため、すぐに取り入れられるものも多いです。
ここでは、ハクビシンが嫌う「光・音・におい」を利用した対策グッズや、実際の侵入経路をふさぐ具体的な方法を紹介します。
忌避グッズの活用法(ホームセンター・ネットで購入可)
ハクビシンは警戒心が強く、環境の変化や不快な刺激に敏感です。その習性を逆手にとって、寄せつけない環境をつくることがポイントです。
ライト(点滅式・センサーライト)
ハクビシンは夜行性で暗い場所を好みます。明るい光や点滅するライトは警戒対象になり、侵入をためらわせる効果があります。
-
センサーライト:人や動物の動きに反応して点灯。玄関・勝手口・畑の周辺などに設置
-
点滅ライト:不規則な点滅がより強い忌避効果をもたらす
-
ソーラー式タイプなら電源不要で設置も簡単
超音波撃退器(周波数可変タイプが効果大)
ハクビシンには聞こえるけれど人にはほとんど聞こえない高周波を出す機器です。最近では、周波数を自動で変化させて「慣れ」を防ぐタイプも登場しています。
-
置き型・壁掛け型があり、屋外や玄関・裏庭などに設置可能
-
モーションセンサー付きなら効率的で省エネ
木酢液やハッカ油スプレー(においで忌避)
ハクビシンは強い刺激臭が苦手です。木酢液(もくさくえき)は木炭を焼いたときに出る煙の液体で、独特のにおいがあります。ハッカ油はスーッとする清涼感のあるにおいで、不快感を与える効果があります。
-
木酢液は水で薄めて、スプレーや布に染み込ませて吊るす
-
ハッカ油は無水エタノール+水で自作スプレーが可能
-
雨や風で流れるため、定期的な再施工が必要
トゲ付きネットや畑用ガードフェンス
畑や庭に侵入させないためには、物理的なバリアも有効です。ホームセンターでは、防獣ネットやトゲ付きフェンスなども手に入ります。
-
柵の高さは最低でも60cm〜80cm以上が理想
-
地面とのすき間がないよう、ペグやブロックで固定
-
果樹の周りは囲い込みで重点的に守るのが効果的
侵入を防ぐ!屋根裏や床下のチェックポイント
忌避グッズだけでなく、ハクビシンが入ってこられないようにする封鎖作業も大切です。
特に屋根裏や床下は、ハクビシンが日中隠れる場所としてよく使われます。
チェックすべき場所:
-
エアコンの配管まわり(パテのひび割れ)
-
通気口・換気口(メッシュの破れ、ふたのゆるみ)
-
軒下や天井裏の小さな穴(3cmのすき間があれば侵入可能)
-
床下の通風口(古い住宅では無防備になっていることも)
対策方法と資材:
-
パンチングメタルや金網をカットして塞ぐ
-
ステンレス製の防獣ネットは耐久性・通気性に優れる
-
ホームセンターで購入可:金網、タッカー、シリコン、すき間テープなど
塞ぐときは、完全に出入り口をふさぐ前に、ハクビシンがいないことを必ず確認してください。
もし中にいた状態で封鎖してしまうと、パニックを起こしたり、壁や天井に大きな損傷を与える恐れがあります。
これらの対策を組み合わせることで、「入れない」「近づかせない」「居心地の悪い場所にする」ことが可能になります。
次の章では、こうした対策の中でも見落とされがちな「フンの処理と清掃」について詳しく解説します。再発防止には、目に見えないニオイや痕跡の除去も重要なカギになります。
ハクビシン対策の備え:フンの片づけと消毒は再侵入防止に必須

ハクビシンの対策というと、追い出したり侵入口を塞いだりすることに注目しがちですが、実はフンの処理と消毒も非常に重要です。
なぜなら、放置されたフンが「ここは安心できる場所」とハクビシンに再認識させてしまう可能性があるからです。
また、フンには悪臭や雑菌が含まれており、健康リスクも見過ごせません。
ハクビシンの糞尿は強烈なニオイと衛生リスク
ハクビシンのフンには、非常に強い臭いがあります。彼らには“ためフン”の習性があり、同じ場所に繰り返し排泄するため、悪臭がこもりやすくなります。
このニオイはハクビシン自身にとっても重要な“マーキング”の役割を果たしており、自分の縄張りを示す目印として利用されているのです。
つまり、フンを放置しておくと、「ここは前に住んでいた場所だ」とハクビシンが再び戻ってくるきっかけになってしまうのです。
また、ハクビシンの糞尿にはダニやノミ、病原菌が含まれていることもあり、アレルギーや皮膚トラブル、呼吸器系の症状など、健康面のリスクも無視できません。
特に小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、早めにしっかりと対処することが重要です。
掃除と消毒のポイント
ハクビシンのフンを安全に処理するには、感染予防を意識した装備と手順が欠かせません。
室内や屋根裏のフンの掃除手順:
-
ビニール手袋とマスクを着用(できればゴーグルも推奨)
-
新聞紙などでそっと包み込み、ビニール袋に密封
-
使用済みの手袋や掃除道具も一緒に廃棄する
-
フンがあった場所を塩素系の消毒液でしっかり拭き取り・噴霧
-
最後に換気をして、空気中のニオイや菌もリフレッシュ
消毒には、市販のハイター(次亜塩素酸ナトリウム)を水で薄めて使用すると効果的です。
市販の「動物用消毒スプレー」やアルコール系消毒液でも代用可能ですが、糞尿には塩素系がより強力です。
畑や屋外でフンを見つけた場合:
-
フンをそのまま土に埋めないこと。菌や寄生虫が土壌に広がる危険があります。
-
可能であれば焼却処分が理想ですが、自治体のルールに従って処理してください。
-
畑の場合は、その場所の作物はしばらく収穫せず、消毒・乾燥を十分に行うのが安全です。
フンの処理と消毒は、再発防止と衛生管理の両面から見ても、非常に大切なステップです。
いくら侵入口をふさいでも、ハクビシンにとって「においが残っている=まだ自分の場所」と感じられてしまえば、何度でも戻ってきてしまいます。
このステップを丁寧に行うことで、より長期的なハクビシン対策につながります。
次の章では、ハクビシン対策において意外と知られていない“法律面の注意点”についても触れていきます。対策のつもりでうっかり違反してしまわないよう、知っておきたい情報を整理してお伝えします。
ハクビシンの間違った対策は法律違反になることも
ハクビシンの被害に悩まされていると、「もう捕まえてしまいたい」「どうにかして追い払いたい」と思う気持ちはよくわかります。
しかし、ハクビシンは単なる害獣ではなく、法律で保護されている動物であることをご存知でしょうか?
知らずに自己判断で捕獲・駆除してしまうと、思わぬトラブルや法律違反による罰則の対象になる可能性があります。正しい知識を身につけて、適切な対策を取りましょう。
ハクビシンは鳥獣保護管理法で守られている
ハクビシンは「鳥獣保護管理法」という法律によって守られており、一般の人が許可なく捕獲・殺処分することは禁止されています。
たとえ家の中に侵入していたとしても、許可なくワナを仕掛けたり、叩いたりすることはNGです。
知らずに捕まえてしまった場合でも、法律違反となり、
-
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
また、万が一けがをさせてしまった場合は、さらに重い罰則となるケースもあります。
「うちは田舎だし…」「自分の家なんだから大丈夫」などと軽く考えず、法律に則った方法で対応することが大切です。
許可を取るか、専門業者に依頼を
ハクビシンを捕獲・駆除したい場合には、まず自治体の担当窓口(環境課や自然保護課)に相談しましょう。
地域によっては、被害状況を申請することで捕獲許可書の交付を受けることができます。
ただし、この申請には書類の提出や審査、時間がかかる場合があり、すぐに対応したい方には不向きかもしれません。
そんなときにおすすめなのが、害獣駆除の専門業者に相談することです。
-
捕獲・駆除に必要な申請手続きは業者が代行してくれる
-
再発防止のための封鎖工事や清掃・消毒も対応可能
-
無料調査や見積もり対応のある業者なら、安心して相談できる
法律を守りながら確実に対策を行いたいなら、こうしたプロのサポートを活用するのがもっとも安全で確実な方法です。
ハクビシンの被害対策は、ただの「自己防衛」では済まされない場面もあります。
適切な手順を踏んで、合法かつ安全な方法で対応することが、被害を減らすだけでなく、後々のトラブルを避けるためにも重要です。
次の章では、実際に効果的な対策を「追い出し→封鎖→予防」のステップで整理しながら、まとめとしてご紹介します。長期的に安心できる環境をつくるためのポイントを押さえておきましょう。
福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の
「害獣駆除」ならお電話1本で駆け付けます!
0120-640-551
ハクビシンの効果的な対策は「追い出し+封鎖+予防」

ハクビシンの対策でよくある失敗が、「追い出したら終わり」と思い込んでしまうことです。
実際には、ハクビシンはとても賢く執着心の強い動物です。一度住みついた場所には強い帰巣本能をもって再び戻ってこようとします。
そのため、追い出したあとに何をするかが再発防止のカギになります。
一時的な追い出しだけでは再発リスクが高い
光や超音波、においなどでハクビシンを一時的に追い出すことはできますが、それだけでは不十分です。
一度外に出たからといって、放置していればまた戻ってくる可能性が高いのです。
効果的な手順は、以下の3ステップです。
-
追い出し(ライト・音・忌避剤など)
-
侵入口の封鎖(すき間や穴をパンチングメタル・ネットでふさぐ)
-
清掃と予防(フンの除去とにおい消し、再侵入させない生活環境づくり)
この順番をしっかり守ることで、ハクビシンに「ここはもう安全な場所ではない」と認識させ、戻ってこさせない状態を作ることができます。
忘れがちな“生活習慣”の見直し
封鎖や掃除といった物理的な対策だけでなく、日常の生活習慣を見直すことも大切です。
ハクビシンは食べ物のにおいに非常に敏感で、わずかなエサでも引き寄せられてしまいます。
気をつけたいポイントは以下の通りです。
-
ゴミ袋は必ずフタ付きのゴミ箱に入れる
-
残った果物や野菜を庭や畑に放置しない
-
ペットフードを屋外に出しっぱなしにしない
-
畑の果実や作物は、熟したらすぐに収穫する
これらのちょっとした習慣が、ハクビシンにとっては「エサがある家」「安全に暮らせる場所」という認識につながってしまいます。
ハクビシン対策において、ハクビシンの再発を防ぐためには、追い出し+封鎖+予防の3つをセットで行うことが不可欠です。
どれか一つでも欠けると、また元の状態に逆戻り…なんてことにもなりかねません。
しっかりと計画を立て、順を追って対策を進めていきましょう。次の章では、今回の記事のまとめと、最終的に安心を得るためのポイントを整理してお伝えします。
まとめ:ハクビシン対策は「知識+行動」がカギ
ハクビシン対策で大切なのは、「知識」と「行動」をセットで意識することです。
被害のサインを見逃さず、どのような習性を持った動物なのかを正しく理解することが、効果的な予防の第一歩になります。
今回ご紹介したように、光や音、においを利用した忌避グッズや、侵入口の封鎖、フンの処理と消毒など、自宅でもできる対策はたくさんあります。
しかし、被害が深刻な場合や、法律が絡む捕獲や駆除が必要なときは、無理をせずに専門業者に相談することが安心かつ確実な方法です。
特に、屋根裏の封鎖や清掃作業、捕獲の申請手続きなどは個人では限界があります。無料調査を行ってくれる業者も多いので、早めに相談することで被害の拡大を防げます。
家族の安全と、住まいの快適さを守るためには、放置しないことが何より大切です。
「なんとなく気になる…」と感じた段階で、対策を始めておくことで、後悔しない結果につながります。
知識をもとに一歩を踏み出し、安心できる住環境を整えていきましょう。
最後に.
こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。
【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?