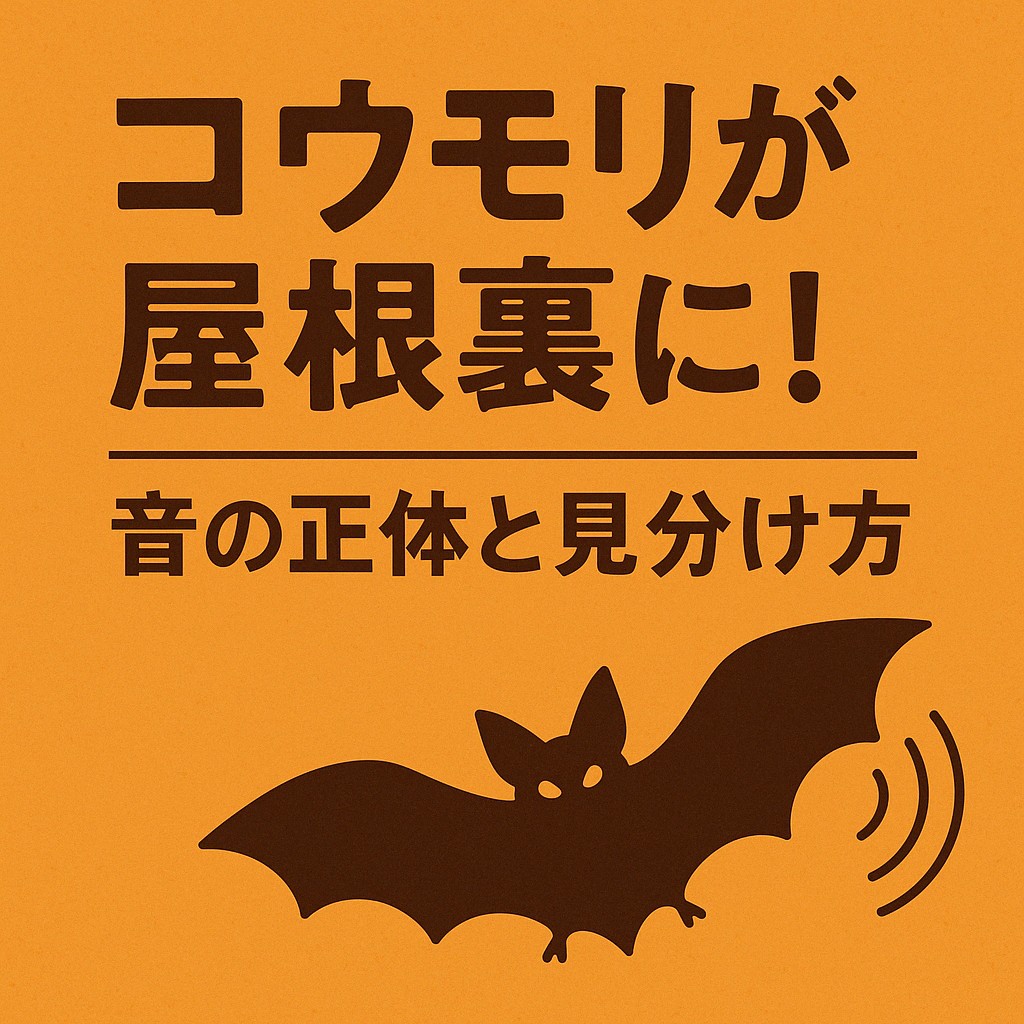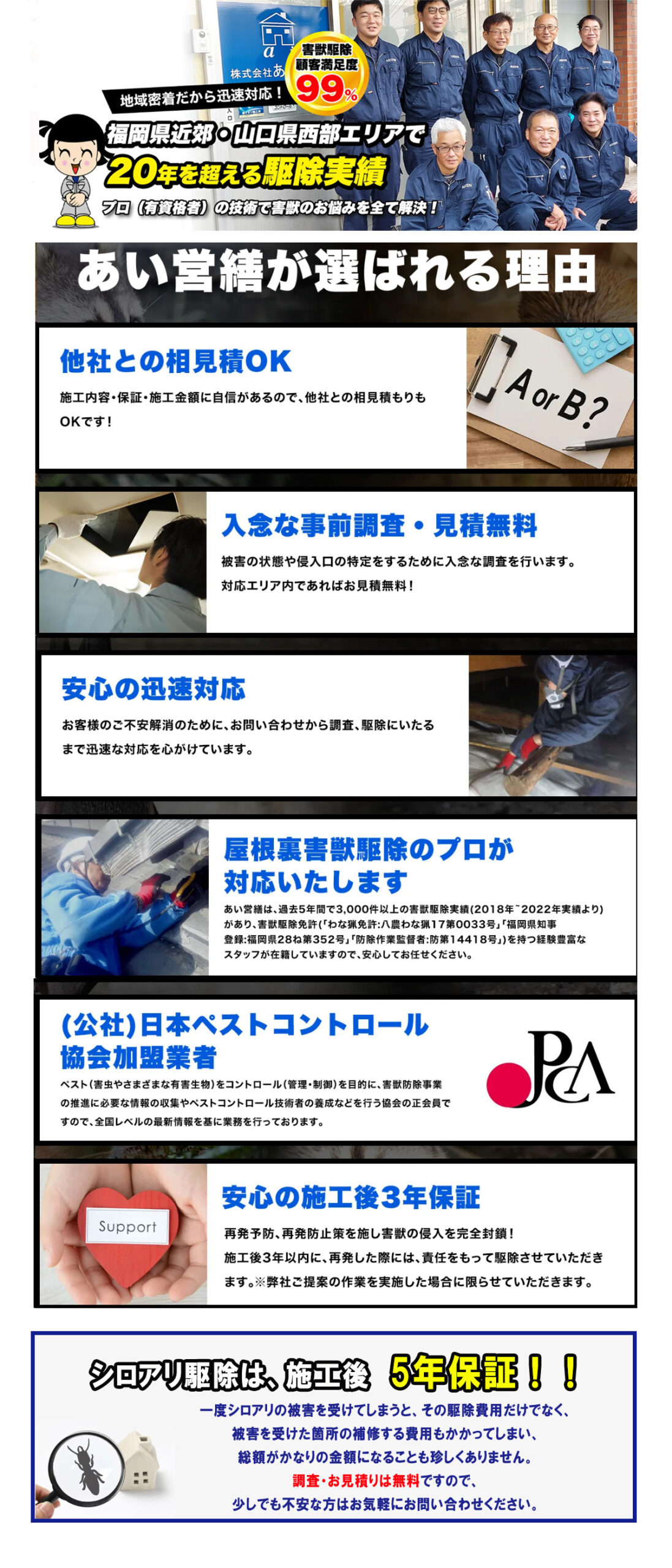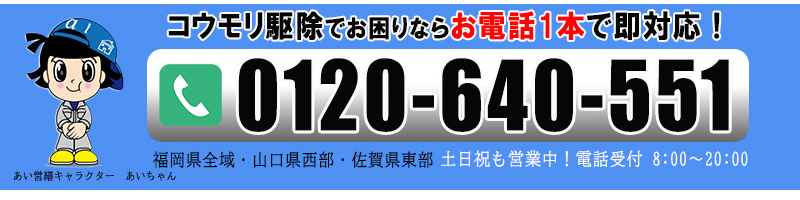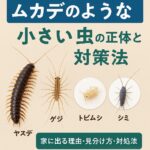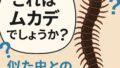夜、静かにくつろいでいるときに、「カリカリ…」「バサバサ…」といった音が屋根裏から聞こえてきたことはありませんか?
音の正体がわからず、「まさか泥棒?それとも動物?」と不安になる方も多いと思います。
そんなとき、可能性のひとつとして考えられるのが「コウモリ」です。
コウモリは意外にも住宅に侵入して棲みつくことがあり、特に屋根裏や壁の中に潜んでいることも珍しくありません。
ただし、音だけで「コウモリだ!」と決めつけるのは危険です。実際には、ネズミやイタチなど他の動物であるケースも多く、それぞれに動き方や音の特徴に違いがあります。
本記事では、「屋根裏で音がするけど正体がわからない…」とお悩みの方に向けて、
コウモリの出す音の特徴や他の動物との違い、見分け方のポイントをわかりやすく解説します。
また、もしそれがコウモリだった場合、どのように対処すべきか、自力でできること・業者に頼むべきタイミングなども合わせてご紹介していきます。
まずは、音の正体を見極めることから始めましょう。
記事のポイント
●コウモリが屋根裏に潜んでいる際の音の特徴がわかる。
●ネズミやイタチとの音の違いや見分け方が理解できる。
●コウモリ被害のサイン(フン・臭い・侵入口)を確認する方法がわかる。
●自力での追い出し方法と専門業者への相談の目安が理解できる。
屋根裏で聞こえるコウモリの音とは?

屋根裏から「カサカサ…」「バサバサ…」という音がするとき、それが本当にコウモリなのか、それとも別の動物なのかを判断するのは意外と難しいものです。
ここでは、コウモリが発する音の特徴と、ネズミやイタチなど他の動物との違いをわかりやすく解説していきます。
コウモリが出す音の特徴(夜間・壁・天井裏)
コウモリが家の屋根裏や天井裏に潜んでいる場合、特に夜22時〜明け方にかけて音がすることが多いです。これはコウモリが夜行性であることと関係しています。
よくある音の特徴:
コウモリは体が軽く、ネズミよりも柔らかく静かな動きをするため、音は比較的軽く小さい印象です。
ただし、羽を広げたときや飛び立つ直前には、一瞬だけ大きな羽音がすることがあります。
また、コウモリは鳴き声をあまり発しないため、「鳴き声が聞こえない=コウモリの可能性が高い」と判断されることもあります。
(実際は超音波で鳴いていますが、人間の耳では聞き取れません。)
ネズミ・イタチとの音の違い
屋根裏で音がする動物としては、コウモリのほかに「ネズミ」や「イタチ」なども代表的です。
それぞれの音の違いを比較してみましょう。
ネズミの音の特徴:
ネズミはコウモリよりもやや重みのある音がし、継続的に「動いている感じ」が伝わってくるのが特徴です。
イタチの音の特徴:
-
「ドタドタ」「ガサガサ」と重たく粗雑な音
-
ジャンプや跳ねるような動きで天井板が鳴ることも
-
夜行性で、主に深夜から早朝に活動
イタチは体重があるぶん音も大きく、まるで人が歩いているような錯覚を起こすこともあります。
コウモリ特有の音の見極め方
コウモリはネズミやイタチに比べて音がやや控えめです。
それでも、「羽ばたく音」と「静かに這うような接触音」が混ざっていると感じたら、コウモリの可能性が高いです。
見極めポイント:
-
音が軽くて不規則/壁や天井の隙間に集中している
-
夜間限定で音がする(昼間は静か)
-
音のあとにフンやしみが見つかる
コウモリは非常に狭い隙間からでも出入りするため、換気口や屋根の隙間、エアコンのダクト付近なども音が聞こえるポイントになりやすいです。
音の特徴を正確に掴むことで、対処法を誤らずに済む可能性が高まります。
次の章では、「音だけでは断定できない場合のチェック方法」や、フン・臭いといった他のサインの確認ポイントをご紹介していきます。
屋根裏の音が気になる方は、ぜひ引き続き読み進めてください。
音だけでは判断できない?その他のサイン

屋根裏から「カサカサ」「バサバサ」といった音が聞こえてきたとき、多くの方がまず音の正体に注目します。
しかし、音だけで「それがコウモリかどうか」を確定するのは難しいのが現実です。
ここでは、音以外にも注目すべきサインとして、フンや臭い、侵入口の形跡について詳しくご紹介します。
コウモリのフンや臭いに注意
もし家にコウモリが棲みついている場合、**音以上に確実な証拠となるのが「フン」や「臭い」**です。
コウモリのフンは小さくても特徴的なので、一度見ておけば見分けやすくなります。
黒くて細長いフンが見つかったら要注意
ネズミのフンと似て見えますが、乾いた状態で粉状になりやすいのがコウモリの特徴です。
もし掃除中や荷物整理の際にこのようなフンを見つけた場合は、手袋とマスクを着用して慎重に処理してください。
強烈なアンモニア臭にも注意
天井にシミができていたり、換気をしてもニオイが消えない場合、コウモリのフン尿被害が進行しているサインかもしれません。
屋根裏のどこから侵入?チェックポイント
音やフンを発見した後は、コウモリがどこから侵入しているのかを突き止めることが重要です。
コウモリは体が小さく、3cmほどのすき間があれば入り込むことができると言われています。
主な侵入口として多い場所
-
換気口(外壁や軒下にある金網部分):網が劣化しているとコウモリが通過できる
-
屋根瓦のすき間や破損部:屋根と外壁の境目は特に注意
-
エアコンの配管口・通気ダクト周辺:パテの劣化や隙間からの侵入
-
屋根裏の通風孔・ひさし裏:人の目に触れにくく、安全な隠れ場所になる
侵入口の確認方法
小さな隙間でも見逃さず、光を当てる・風の通りを感じる・虫の出入りを見るなど五感を使ってチェックするのがポイントです。
「夜に音がしたけど姿が見えない」というときこそ、フン・ニオイ・侵入口の確認が重要です。
コウモリは繁殖力も強いため、発見が遅れると被害が拡大することもあります。
次の章では、実際にコウモリがいたときにどうやって追い出すか、駆除するかの方法を詳しくご紹介します。
壁の中や天井からの音にも注意

「屋根裏から音がすると思っていたら、実は壁の中だった…」というケースは意外に多く、コウモリの潜伏場所は天井裏だけに限りません。
壁のすき間や構造材の裏側など、思わぬ場所にねぐらを作っていることもあるため、注意が必要です。
ここでは、壁の中や天井から聞こえる音と、コウモリの潜伏ポイント、そして見つけ方のコツについて解説します。
コウモリは壁のすき間に潜むことも
多くの人が「屋根裏にいる」と思い込んでいますが、コウモリは非常に狭い場所にも潜り込む習性があります。
そのため、壁の中、断熱材の裏、構造材の間などに棲みついていることも珍しくありません。
見逃しがちな潜伏スポット:
-
外壁と内壁のすき間
-
エアコンの配管スペース周辺
-
換気ダクトと断熱材の間
-
屋根と外壁の接合部のひさし裏
壁の内部にコウモリがいると、「カサカサ」「パタパタ」「コンッ」といった音が、天井ではなく“壁から聞こえる”のが特徴です。
また、壁の表面をよく見ると、フンが落ちていたり、薄く黒ずんだ汚れがついていることもあります。
見つけ方と注意点(知恵袋で話題の方法も)
「音はするのに姿が見えない…」そんなときは、音の出入り口や痕跡を探す工夫が役立ちます。
早朝・夕方の観察が効果的
コウモリは夜行性なので、出入りする時間帯はだいたい決まっています。
特におすすめなのは以下の時間帯です。
-
早朝(4時〜6時):ねぐらに戻ってくる時間
-
夕方(18時〜19時):活動を開始する時間
この時間帯に、家の外から屋根の縁、換気口、エアコン配管、ベランダ裏などを静かに観察してみてください。
小さな影がすっと飛び出してくるようなら、コウモリの可能性が高いです。
スマホの録音・センサーライトも有効
音を記録しておきたい場合は、スマホのボイスメモ機能や無料の録音アプリを使って、
気になる時間帯に屋根裏や壁のそばにスマホを置いておくと、証拠になる音を拾えることがあります。
また、センサー付きのライトや防犯カメラを設置すれば、出入りする瞬間を可視化することもできます。
音が壁から聞こえるとき、「ネズミかも」と思い込んで駆除を誤ると、逆にコウモリの被害が悪化することもあります。
正確な判断と、適切な観察でコウモリの存在を突き止め、次のステップである「追い出し」や「予防」に進みましょう。
次の章では、コウモリを屋根裏や壁の中から追い出す方法と、再侵入を防ぐポイントについて詳しくご紹介していきます。
コウモリを追い出すには?自力と業者の違い
コウモリが屋根裏や壁の中に棲みついているとわかったら、次に気になるのが「どうやって追い出せばいいのか」ということですよね。
方法としては大きく分けて「自力での追い出し」と「業者に依頼する」2つがあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況やご家庭の環境にあわせて判断することが大切です。
バルサン・超音波・ライトなどの家庭用対策
まずは、自分でできるコウモリ対策を紹介します。いずれも「追い出し」が目的であり、直接の駆除(捕獲・殺処分)は法律上できません。
■ バルサン(燻煙剤)
■ 超音波撃退機
■ 点滅ライト・忌避スプレー
-
センサー付き点滅ライトや常時点灯ライトは、夜行性のコウモリにとって嫌な環境
-
木酢液やハッカ油など、自然由来の忌避スプレーも一定の効果あり
-
ただし、においは時間とともに薄れるため定期的な再噴霧が必要
これらの方法を組み合わせることで、コウモリが「居心地が悪い」と感じて自主的に出ていくことが期待できます。
自力で限界を感じたら業者に相談
自力での追い出しが難しいケースも多々あります。
特に以下のような場合は、早めに専門業者に相談するのが安全かつ確実です。
■ 鳥獣保護管理法の制限
追い出しやフンの清掃、防除工事までは許される範囲ですが、「物理的な駆除」は絶対にNGです。
■ 業者選びのポイント
特にフンの量が多かったり、屋根裏に住みついている期間が長い場合は、清掃・消毒・封鎖工事まで一括で任せられる業者に依頼することをおすすめします。
まずは追い出し、そして再発防止
コウモリ対策で大切なのは、「追い出し」だけで終わらせず、その後にしっかりと侵入口を塞ぐことです。
自力でできる範囲には限界があるため、被害の大きさや心配な点があれば、無理をせず専門の害獣駆除業者に相談することが、もっとも確実な解決策と言えるでしょう。
次の章では、コウモリによる健康や住宅への被害についても詳しくご紹介していきます。
コウモリによる被害と放置のリスク
コウモリが屋根裏や壁の中に住みついてしまった場合、ただの「音の問題」だけでは終わりません。
時間が経つほどに被害は深刻化し、人の健康や住まいの構造にまで悪影響を及ぼすリスクがあるのです。
ここでは、具体的な健康被害と建物へのダメージについて詳しく解説します。
健康被害(ダニ・ウイルス・臭い)
コウモリそのものはおとなしく、直接人を襲うことはありませんが、フンや尿を放置することによってさまざまな衛生被害が発生します。
■ 糞による感染症のリスク
■ ダニ・寄生虫による被害
■ アンモニア臭による生活環境の悪化
建物へのダメージ
健康被害に加えて、コウモリの被害は家そのものの価値や安全性を損なうことにもつながります。
■ 天井や断熱材の腐食
■ 最悪の場合、天井からフンが漏れることも…
放置は絶対NG。早期発見・早期対処がカギ
「音がするだけ」「気のせいかも」と放置していると、被害は確実に拡大していきます。
一度でも音やフン、臭いに気づいたら、早めに原因を特定し、追い出し+封鎖+清掃のセットで対処することが重要です。
まとめ:音の特徴を見極め、早めに対処しよう
屋根裏や壁の中から聞こえる「カサカサ」「バサバサ」といった音――それが本当にコウモリかどうかを判断するのは簡単ではありません。
特に、ネズミやイタチといった他の動物も同じような音を出すため、音だけで断定するのは危険です。
そこで重要になるのが、「音+フン+侵入口」の3点セットです。
● 夜間に軽い羽音や移動音がする
● 屋根裏やベランダに細長く黒いフンが落ちている
● 換気口や屋根の隙間など、コウモリが通れそうな侵入口がある
このような状況が揃っていれば、コウモリが住みついている可能性は高いと言えるでしょう。
被害を放置してしまうと、フンによる衛生リスクや建物の劣化、さらには健康被害につながる恐れもあります。
もし自分での対策に不安がある場合は、早めに専門業者に相談することもひとつの手です。
コウモリは放っておいてもいなくなることはありません。
小さなサインを見逃さず、早めに対処することで、住まいの安心と快適を守ることができます。
最後に.
こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。
【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?
最後までお読みいただきましてありがとうございました。