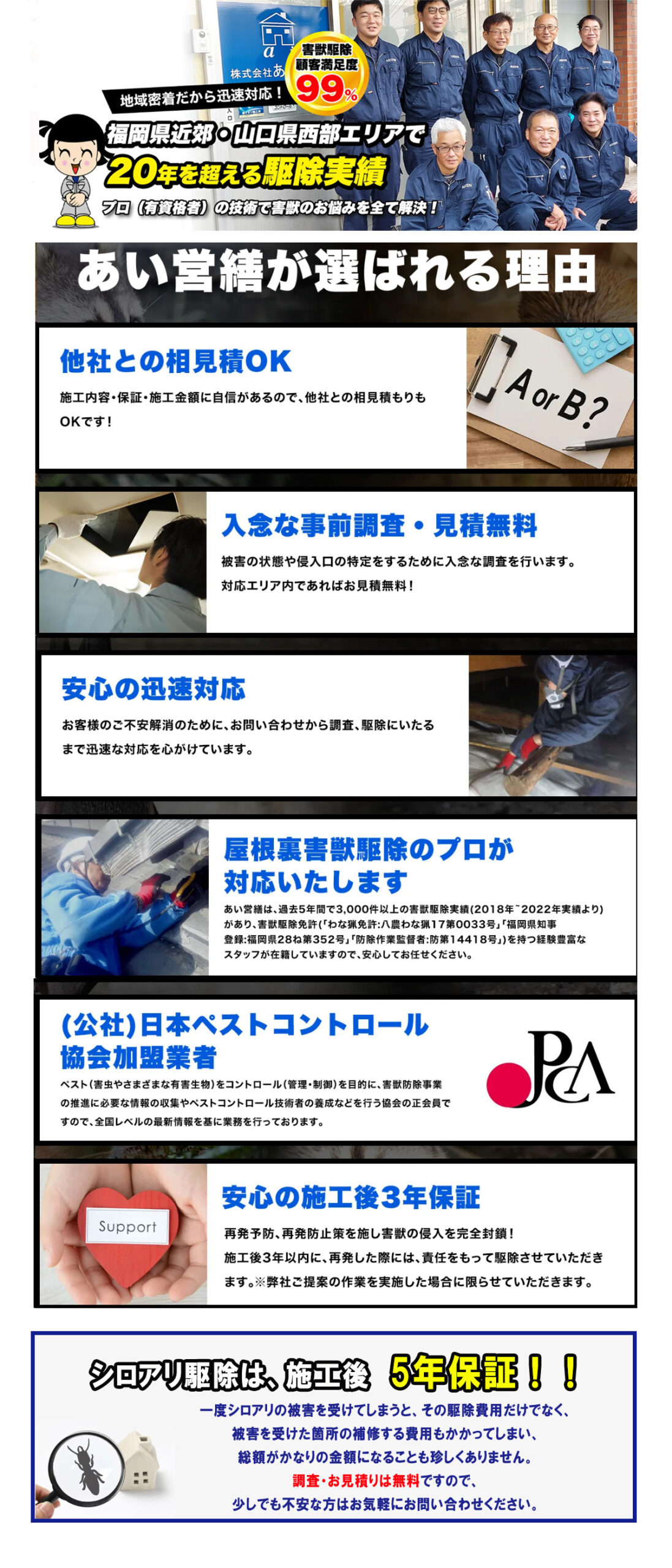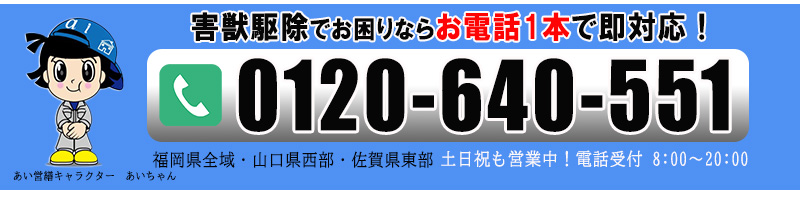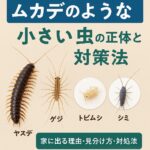朝、庭やベランダに見慣れない足跡が残っていて「これ、何の動物だろう?」と気になったことはありませんか?
夜中にゴソゴソ音がした翌朝、土の上や車のボンネット、ベランダの手すりにくっきりとした足跡が残っていると、不安になるのも無理はありません。
その足跡、もしかしたらアライグマのものかもしれません。
アライグマは見た目がかわいらしい反面、住宅地や畑に現れてはフン尿や騒音、農作物の被害を引き起こす「特定外来生物」として警戒される動物です。
特に、足跡はアライグマが家の近くまで侵入してきている「明確なサイン」であり、早めの対処が重要です。
本記事では、
-
アライグマの足跡の見分け方
-
ハクビシンやタヌキなど他の動物との違い
-
足跡を見つけた後の正しい対処法
について、わかりやすく解説していきます。
足跡を見つけたら、単なる通りすがりではなく「被害の予兆」かもしれません。早めに知識を身につけ、住まいと家族を守る行動につなげましょう。
アライグマの足跡の特徴とは?
屋外や家まわりに残る不思議な足跡。その形をよく観察すると、「これはもしかしてアライグマ…?」と思うことがあるかもしれません。
アライグマの足跡には独特の特徴があり、他の動物と見分ける手がかりになります。ここでは、足跡の形状や見られる場所について詳しく解説します。
足跡の形・大きさ・本数の特徴
アライグマの足跡の最大の特徴は、まるで“人の手”のような形をしていることです。前足・後ろ足ともに5本指で、それぞれの指がしっかり開いているため、手のひらのように見えることがあります。
-
前足のサイズ:およそ5cm前後
-
後ろ足のサイズ:やや大きめで約6〜7cm程度
-
指の向き:前足の指は放射状に開き、後ろ足はやや直線的な配置になる傾向あり
特に前足は、器用にものを掴める構造になっているため、指が長く、爪の跡までくっきり残ることもあります。足跡の中央には肉球の跡があり、全体的に楕円形に広がっているのも特徴です。
また、歩いた軌跡を観察すると、前足と後ろ足の足跡が少し重なるような歩行パターンになることが多く、足跡の並びも独特です。
雪・泥・屋根などで見られる場所と痕跡の違い
アライグマは主に夜間に活動し、屋根裏や庭、畑などを移動します。そのため、足跡が残るシーンは季節や環境によってさまざまです。
■ 雪や泥に残る足跡
-
雪が降った朝、庭や屋根の上にくっきりと指の跡が残っていることがあります。
-
泥や濡れた地面でも同様に、細かい指の形まで確認できることが多いため、見分けやすいタイミングです。
■ 屋根や壁に残る引っかき傷や爪痕
-
屋根への登り降りの際、瓦やサイディングに爪痕が残るケースもあります。
-
特に雨どい、換気口のフチ、ベランダの手すり付近などに、爪でひっかいたような細いスジが見つかることがあります。
アライグマは非常に身体能力が高く、垂直の壁も登ることができるため、高所での足跡も要注意です。
人目につきにくい屋根裏や2階のベランダなどにも侵入してくるため、日頃から周囲のチェックを習慣づけることが大切です。
間違った対策は法律違反になる恐れも
「見つけたから捕まえよう」「物置に閉じ込めて追い出そう」といった対処をしようとしている方は、ちょっと待ってください。
アライグマは外来種であると同時に、「特定外来生物」および「鳥獣保護管理法」の対象動物です。つまり、勝手に捕獲・殺処分することは法律で禁止されており、違反すると罰金や懲役などの処罰の対象になります。
✅ 捕獲や駆除を行うには、原則として自治体への届け出と許可が必要です。
✅ 市町村の環境課・農政課などに相談することで、許可の手続きや対応可能な業者を紹介してもらえるケースがあります。
✅ 現在は無料調査や再発保証付きの専門業者も増えており、法律に則った安心・安全な対応が可能です。
アライグマの足跡を見つけたら、「ただの通りすがりかも」と見過ごさずに、早めの確認・対応をおすすめします。
軽視して放置した結果、大きな修繕費用や健康被害につながるケースもあるため、慎重に、かつ正しい方法で対処することが大切です。
アライグマを駆除・予防する方法
アライグマの足跡を発見したら、それは「ここに住みついている、あるいは通っている」という強いサインです。
被害が拡大する前に、早急な対応が求められます。ここでは、自分でできる予防策と、専門業者に依頼する際のポイントについて具体的に解説します。
自分でできる追い出し&侵入防止策
まずは、アライグマが「この家は居心地が悪い」と感じてくれる環境をつくることが大切です。以下のような忌避グッズや物理的な対策を組み合わせることで、効果的な予防が可能です。
■ 忌避グッズの活用
-
ハッカ油スプレー:爽快感のある香りですが、アライグマにとっては強烈な刺激。侵入口やフンのあった場所に噴霧します。
-
木酢液:煙臭が特徴で、土や屋外の環境にもなじみやすい。畑やベランダなどにも使用可能。
-
センサーライト:夜間の侵入に敏感に反応。突然の光に驚いて近づかなくなります。
-
超音波発生器:人間には聞こえにくい周波数の音を出し、動物に不快感を与える装置。可変周波タイプがより効果的です。
■ 侵入経路の封鎖
アライグマは非常に柔軟な体をしており、わずか3cmのすき間からも侵入可能です。次のポイントを重点的に確認し、封鎖しましょう。
-
屋根裏の通気口や換気口
-
屋外に面した配管周辺や基礎のひび割れ
-
屋根瓦の隙間や軒先のゆがみ
対策グッズとしては、以下のようなものがおすすめです。
-
パンチングメタルや金網:通気性を保ちつつ、動物の侵入をブロック
-
防獣ネット:柔軟で扱いやすく、隙間を埋めるのに便利
-
コーキング材やウレタンフォーム:細かいひびや穴をしっかり密閉
専門業者に依頼する場合のポイント
アライグマは特定外来生物かつ鳥獣保護管理法の対象動物のため、捕獲や駆除には許可が必要です。自力での対応が難しい場合は、専門業者に相談するのが最も安全かつ確実です。
■ 業者選びで確認したいポイント
-
無料調査の有無:現地の状況を見て見積もりしてくれる業者が安心。
-
再発保証の有無:封鎖後の再侵入リスクに対して、アフター対応があると心強い。
-
法律に対応しているか:自治体への申請・許可を代行してくれるかどうかもチェック。
■ 駆除の流れと費用相場(目安)
-
問い合わせ・相談
→ 状況ヒアリング、調査日の調整 -
無料調査・見積もり
→ 屋根裏・床下・屋外を目視確認し、被害の程度と侵入口を特定 -
駆除・封鎖作業
→ 忌避作業、封鎖、清掃・消毒まで一括対応 -
アフターサポート(保証付き)
-
費用の相場感:
小規模な被害:30,000円〜50,000円
中〜大規模(複数作業含む):80,000円〜150,000円前後
※現場の状況や施工範囲により大きく変動します。
被害が小さいうちに自分で対策することは可能ですが、すでにフンや音、悪臭が発生している場合は、速やかに専門家のサポートを受けることをおすすめします。
正しい方法で駆除し、再発を防ぐためには、専門的な知識と技術が欠かせません。家族の安心と住環境を守るためにも、慎重に判断しましょう。
福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の
「害獣駆除」なら電話1本で駆け付けます!